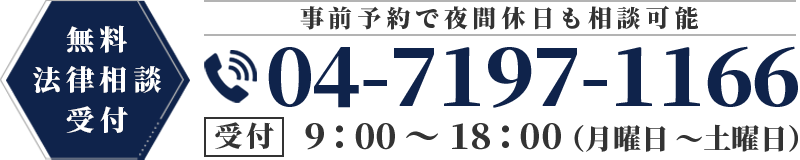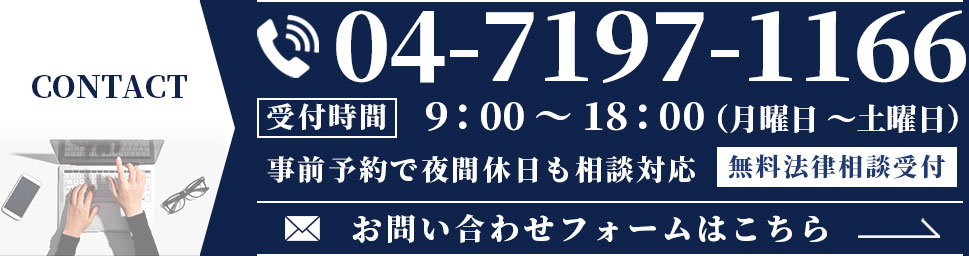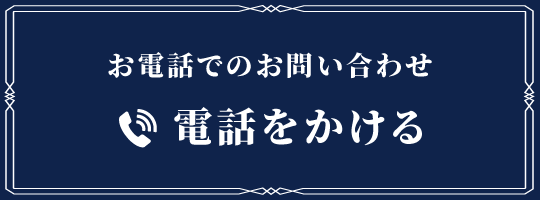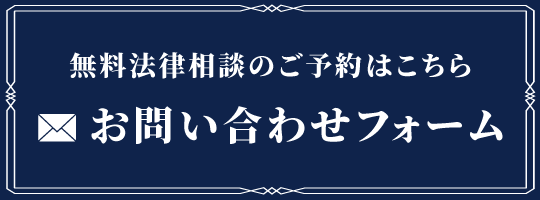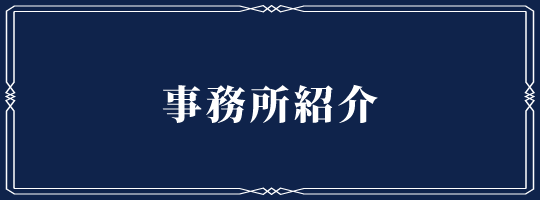遺言書の中で「遺言執行者」に指定された場合、多くの方はどのように対応したらよいか戸惑われることが多いものです。遺言執行者は、遺言者が亡くなられた後、その遺言内容を法的に実現するための非常に重要な役割を負っています。
そこでここでは、遺言書の中で遺言執行者に選ばれた際の具体的な対応方法をわかりやすく解説いたします。
このページの目次
遺言執行者とはどのような立場か?
まず「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現・執行する人物です。主な役割としては、遺言に従った財産の名義変更や遺贈、未成年者の認知や相続人との連絡調整など多岐にわたります。
以下が業務の一例です。
- 遺言書の検認手続き(※公正証書遺言を除く)
- 財産の名義変更・解約手続き
- 遺産分割の実施
- 相続人への連絡・調整
- 特定の遺贈(寄付など)の履行
これは必ずしも専門的な資格を要する職務ではありませんが、手続き上の煩雑さや法的な責任を伴うため、慎重かつ誠実な対応が求められます。
遺言執行者への就任を拒否することはできる?
遺言執行者に指定されても、強制的に就任させられることはありません。
まずは、自分がその責務を果たせるかを冷静に判断しましょう。
以下のような要素を踏まえて検討することをお勧めします。
- 精神的・時間的余裕があるか
- 財産の内容が複雑ではないか(不動産、株式、借金など)
- 相続人間に対立はないか
- 相続税の申告や納付が必要か
- 自分一人で対応できるか、専門家の支援が必要か
遺言執行者に就任しない場合には、相続人に対し、就任しない旨の回答をする必要があります。
相続人その他の利害関係人から、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかを回答するよう催告があった場合に、その期間内に遺言執行者が相続人に対し確答をしない場合には、就任を承諾したものとみなされるので(民法1008条)、注意が必要です。
遺言執行者に就任した後に行う5つの対応
それでは実際に遺言執行者に選ばれた場合、どのような行動をすれば良いのかを詳しくお伝えします。
① 遺言書の確認と次の手順の把握
まず最初に行うのが、遺言書をきちんと確認し、自分が本当に遺言執行者として指定されているか、遺言内容を正確に把握することです。
遺言書が公正証書遺言の場合、公証役場に原本が保管されているため、公証役場から謄本を取得して確認しましょう。
- 遺言書(自筆証書遺言)の場合:
家庭裁判所にて検認手続きが必要です。(1~2ヶ月程度) - 公正証書遺言の場合:
検認手続きは不要。迅速に執行手続きを開始できます。

② 相続人への通知・連絡とコミュニケーション
遺言執行者に選ばれたら、速やかに相続人と連絡を取り、遺言執行者に就任したこと及び遺言書の存在と内容の概要を伝えましょう。
法的にも、遺言執行者は相続人全員に対して遺言内容を伝える義務(民法1007条2項)があります。
【伝える内容】
- 遺言執行者に就任すること
- 遺言内容
- 通知方法:特別な様式はありませんが、書面等で明確に伝えることを推奨します。

③ 相続財産の調査と管理
財産を特定し、その状況を調査して正確に把握しましょう。
また、遺産が確保されるまでの期間、不正や消失を防ぐために適切な管理を行う必要があります。
- 全体の財産状況を調査:銀行預金、不動産、株券、投資信託、保険契約など。
- 不動産については登記内容を確認、預貯金については残高証明を取得することが推奨されます。
- 財産目録を作成し、相続人に開示する。また財産の管理責任は遺言執行完了まで遺言執行者が負います。

④ 各種財産の名義変更・遺産分配手続き
財産調査・財産目録作成後、実際の相続財産の名義変更手続きを進めていきます。
この手続きこそ遺言執行者の中心的な業務となります。
- 不動産の場合:
遺言に基づき、法務局にて相続登記手続き(約1〜2ヶ月程度) - 金融財産の場合:
銀行等に対し、解約・払い戻し手続きや口座名義変更(約1〜2ヶ月程度) - 株式など有価証券の場合:
証券会社にて名義変更手続き(おおむね1ヶ月〜2ヶ月程度)

⑤ 相続人への報告
- 財産の分配結果を説明し、これは書面で残しておくことが望ましいと考えます。
遺言執行者が特に注意すべき点
遺言執行者は遺言を適法かつ忠実に執行する義務があります。以下の点は特に注意しましょう。
- 遺言執行者には、職務を適正に遂行しないと損害賠償請求される可能性があります。
- 遺言内容に疑問や解釈の相違がある場合、放置せず専門家に相談(弁護士など)するのが適切です。
- 手続きにかかる期間はおおむね3か月〜6か月が目安。期限内に滞りなく完了させることが望ましいです。
遺言執行者を辞退したい場合の手続き
突然遺言執行者に指定された場合、業務量や責任の重さに不安を感じる方も少なくありません。法的に辞退することは可能ですが、辞退したい場合は以下のような手続きで進めます。
- 辞退届を早期に(おおむね遺言者の逝去後3ヶ月以内に)家庭裁判所に提出。
- 必要に応じて新たな遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
遺言執行業務の報酬について
遺言執行者は任務の報酬を受け取ることが可能です。遺言書に報酬が記載されている場合はそれを遵守し、記載がなければ相続人と協議のうえ決定するか、家庭裁判所に額の決定を申立てることができます。
一般的な目安として、財産総額の1%~3%程度(1,000万円以下の場合は30万円前後)のケースが多くみられます。
まとめ
遺言執行者は、故人の遺言を忠実に履行する重要な役割であると同時に、相続人間のトラブル防止にもつながる重要な存在です。しかし、責任を伴う作業であるだけに、不安や疑問を感じたらできるだけ早めに専門家(弁護士)に相談しましょう。
当法律事務所でも、ご相談者が安心して業務を全うできるよう全面的にサポートさせていただきます。