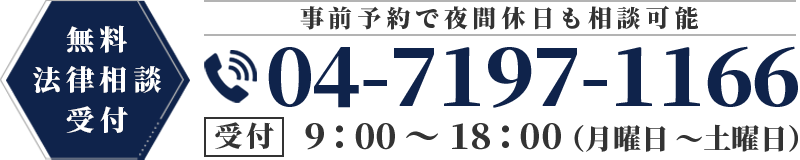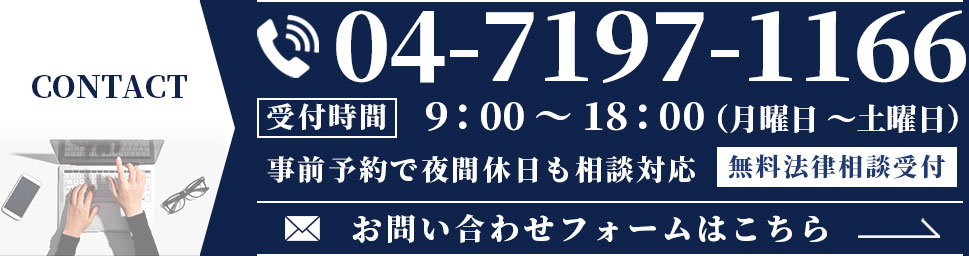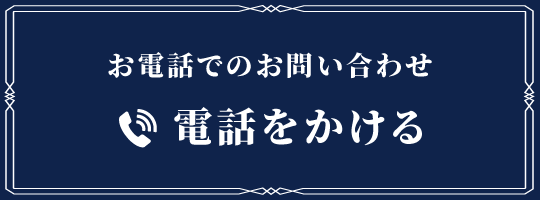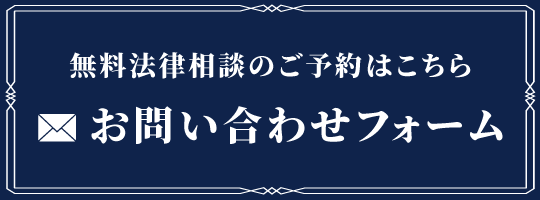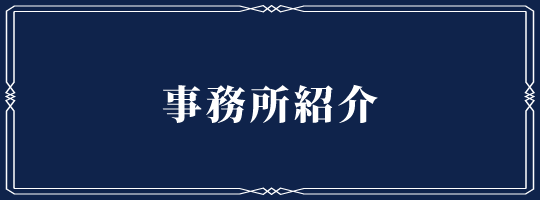遺言書は大切な財産を次世代へ円滑に引き継ぐために非常に重要な役割を持ちます。
しかし、遺言書には法律的な要件があり、それらを満たしていない場合、せっかく作成した遺言が無効となるリスクがあります。
それを防ぐために、本記事では遺言書が法律上有効かどうかをご自身で確認するための重要なポイントをわかりやすくご紹介します。
このページの目次
遺言書に共通する有効要件とは?
遺言書には主に次の3つの形式があります。
それぞれに基本的な有効要件がありますが、特に注意すべきなのは自筆証書遺言です。
- 自筆証書遺言:
ご自身が全文を手書きで作成する遺言書 - 公正証書遺言:
公証人が作成し、公証役場に保管している遺言書 - 秘密証書遺言:
遺言の存在だけを公証人が証明し、内容を秘密にする遺言書
自筆証書遺言の主な有効性チェックポイント
① 自筆で全文が記載されているか
自筆証書遺言では、全文を本人が自分の手で書かなければなりません。パソコンやスマートフォンで入力したり、代筆してもらったりした場合は無効となります。
ただし、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書によることを要しません(民法968条2項前段)が、各ページに署名と押印をする必要があります。
② 日付が正確に記載されているか
作成された年月日が明確に記載されているかを確認しましょう。日付が曖昧、もしくは記載漏れの場合、自筆証書遺言は無効になります。
「令和7年4月」など日付が特定されていない形式は不可であり、「令和7年4月15日」といった具体的な日付の記載が必要です。
③ 本人の署名と押印があるか
遺言書の末尾等に本人による自筆の署名と押印があることが必要です。署名漏れや押印漏れがある場合、遺言書は無効です。
押印は紛争防止という点からは、実印が推奨されますが、認印でも問題はありません。ただ、後日の紛争回避のため実印を使用することを推奨しています。
④ 訂正が適法かどうか
民法は、加除その他の変更について、「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条3項)と方式を定めています。
- 遺言者が加除その他の変更の場所を指示し、
- これを変更した旨を付記し
- 特にこれに署名し、
- 変更の場所に印を押す
ことが、加除その他の変更の要件となります。
具体的には、加除その他の変更の場所を記載したうえで(①)、これを変更した旨(削除や追加、改める場合はその文言)を付記し(②)、その(①及び②の)記載がされた箇所に署名をする(③)必要があります。その上で、「変更場所に」押印をする必要があります(④)。
⑤ 意思能力があったかどうか
遺言を作成した際に十分な意思能力(自分の意思を正常に判断・表示できる能力)があったかどうかも有効性に影響します。
高齢者の場合や認知症状がある場合などでは、医師の診断書や介護職員の証言などで遺言能力が確認できると紛争を防ぎやすくなります。
公正証書遺言の有効性チェックポイント
公正証書遺言は公証人関与の下で作成されるため、一般的に自筆証書遺言より有効性が高いとされますが、それでも以下の項目については確認してください。
- 遺言者が公証人の前で、遺言の内容をはっきり伝えているか
- 公証人の前で、遺言の内容をはっきり伝えているか
- 2人以上の証人が公証人と共に立ち会い、遺言の内容確認や署名押印をしたか
- 証人が証人としての資格を有する者か(未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族等でないか)
- 作成された公正証書遺言に署名押印した遺言者本人が内容を理解・承諾しているか
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて方式違背等で無効となる可能性が抑えられますが、手続き上の不備がないかを改めて確認することが重要です。
遺言書作成者が亡くなった後の手続き(検認)に注意
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言作成者が亡くなった後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必須です(法務局で保管されている遺言は検認不要)。
検認を行わないまま遺言の開封や処分を行うと、5万円以下の過料処分の対象になるため必ず注意しましょう。
※公正証書遺言の場合や自筆証書遺言保管制度を用いている場合は裁判所での検認手続きが不要です。
遺言書の保管にも注意しましょう
自筆証書遺言の場合、遺言書の保管方法について法律上の制限はありませんが、紛失や偽造を防ぐため、法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月から施行)を活用すると安心です。
この制度での保管手数料は1通につき3,900円です(2025年現在)。法務局で保管された遺言は検認不要にもなります。
- 遺言書を安全に保管することで改ざんや紛失のリスクを防ぐ
- 相続発生後の手続きの負担を減らす(検認不要)
遺言書が無効となることを防ぐために弁護士に相談しましょう
遺言書が無効と判断されると、ご家族間で不要な争いやトラブルが発生する恐れがあります。有効な遺言書を作成するためには専門家の適切なアドバイスが重要となりますので、作成前、あるいは作成後にも弁護士に相談し万全を期しましょう。
当事務所では、相続問題に詳しい弁護士が、お客様の遺言作成から相続手続きまでサポートいたします。
まとめ
遺言書の有効性を判断するためには、自筆・日付・署名・押印や訂正の仕方、遺言能力など複数のチェック項目があります。
ご自身の遺言が正確に要件を満たし、法的に有効であるかどうかご不安な場合には、早めに専門的アドバイスを受けることをお勧めします。遺言書の正しい確認や相続問題でお悩みの際は、ぜひ安心して当事務所にご相談ください。