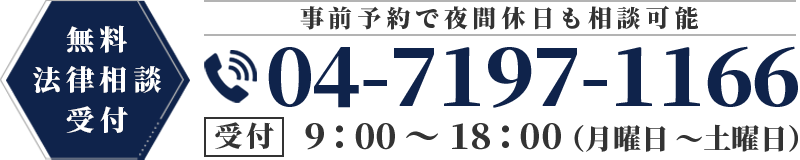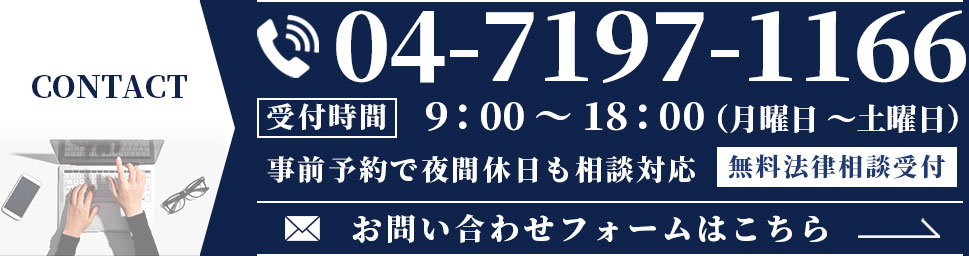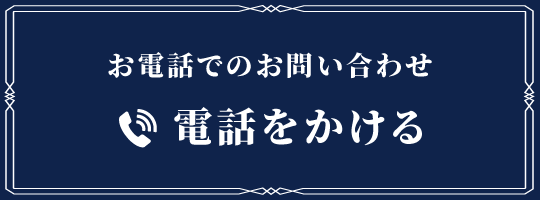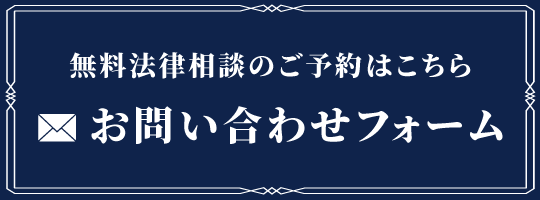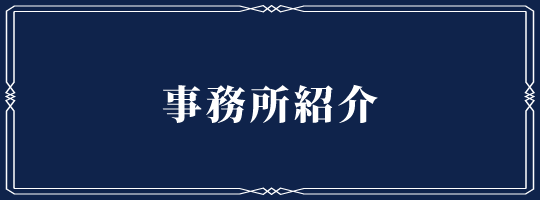遺言は亡くなった方が自身の意思を明示し、財産の帰属の決定や、遺産分割の方法を指定する重要な法的手段です。しかしながら、その遺言に不備があったり、遺言作成時の状況に問題がある場合、遺言が「無効」となる可能性があります。
このページでは、遺言の無効を主張する具体的な法的要件と、その注意点についてわかりやすく解説いたします。
このページの目次
遺言が無効になる主な4つの場合
作成された遺言が法律的に無効になる理由は主に以下の4点に分類されます。
遺言に対して異議がある場合、これらの中から該当するケースがないか確認する必要があります。
① 遺言能力(意思能力)の欠如
遺言を書くためには、「遺言能力」(意思能力)を備えていることが必要です。
遺言能力とは、自分の置かれた状況や自らの行動の結果を理解し、判断できる能力を指します。この能力が欠けている状況で作成された遺言は、法的に無効と判断されます。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 認知症や精神疾患等の病気によって、遺言作成時に適切な判断能力が欠けている場合
- 重病や薬の服用により意識や判断力が正常でない状況で作成された場合
遺言能力を欠いているかどうか争う場合には、医師の診断書や治療記録が有効な証拠になります。
② 遺言書の方式不備(形式不備)
遺言書は法律で定められた一定の方式・形式を厳密に守っている必要があります。形式的な要件を満たさない遺言書は無効となります。
特に、自筆証書遺言や公正証書遺言それぞれに異なる方式が求められるため、各種類の遺言書の形式を確認する必要があります。
例えば、自筆証書遺言に求められる形式は以下の通りです。
- 遺言書全文が遺言者本人による自筆で書かれていること(一部例外を除いてパソコン・ワープロ不可)
- 作成年月日が明記されていること
- 署名・押印が確実にされていること(署名だけ、押印だけでは十分ではなく、基本的に両方が必要)
これらの要件に欠陥がある場合は遺言自体が無効となります。
③ 遺言内容への不当な干渉(詐欺、脅迫、誘導など)
遺言は本人の自由意思に基づいて行われるべきものです。そのため、第三者が遺言書の作成に不当な影響を与え、詐欺、強迫または不当に誘導した場合、その遺言は無効となります。
- 脅迫や暴力などにより、本人の自由な判断が妨げられた場合
- 不正な誘導や虚偽の情報によって遺言の内容が操作された場合
- 第三者が自分に有利になるよう不当に働きかけ、遺言の内容に影響を与えた場合
これらの場合には、関係者の証言、メールや文書の記録、音声記録など、具体的な証拠を集めることが重要になります。
④ 遺言書の偽造や変造
遺言書の偽造や変造(内容を勝手に書き換えること)など、不正な行為が行われた遺言書は当然無効となります。偽造や変造の事例としては次のような場合が考えられます。
- 本人ではない第三者が遺言者になりすまして遺言を作成した場合(偽造)
- 遺言書作成後に遺言書の一部を無断で書き換えた場合(変造)
遺言書の筆跡鑑定や、遺言書が保管されていた状態の確認が重要な証拠となります。
遺言無効を主張する方法と手続きの流れ
無効理由に該当する可能性があり、それを法的に主張したい場合、遺言無効確認訴訟を地方裁判所に提起する必要があります。
以下に主な手続きの流れと注意点を示します。
弁護士のサポートのもと、遺言内容や形式的要件を詳しく検証します。
医師の診断書、筆跡鑑定結果、関係者の証言記録、通信記録など、遺言作成時の状況証拠を迅速に収集します。
地方裁判所に遺言の無効を求める訴訟を提起します。訴訟には明確な期限はありませんが、速やかな対応が望ましいでしょう。
裁判所で双方の主張と証拠を提示し、裁判官が十分な審理を経て対応を判断します。
遺言の無効を主張する場合のおおよその期間
遺言無効確認訴訟は一定の期間を必要とします。以下は、通常の期間目安をまとめたものです。
| 手続き内容 | おおよその期間 |
| 証拠収集・訴状準備 | 3~6か月程度 |
| 訴訟提起後の審理(裁判所での審理) | 6か月~1年以上(事案により異なる) |
まとめ
遺言無効を主張するためには、十分な証拠収集と法的知識に基づいた的確な主張が必要です。この手続きには専門性が高いため、ご自身だけで対応すると負担が大きく、有効な主張や証拠収集が難しくなる可能性があります。
当事務所では遺言無効確認訴訟をはじめ、多数の相続問題の解決実績があります。遺言の効力に関してお困りの際には、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、ご依頼者様の疑問や不安を解消し、最適な法的サポートをご提供させていただきます。