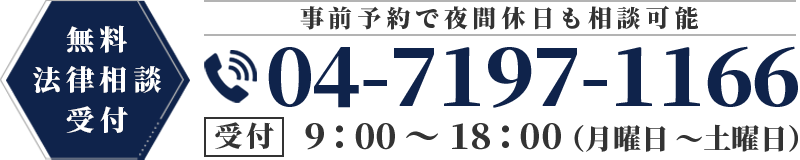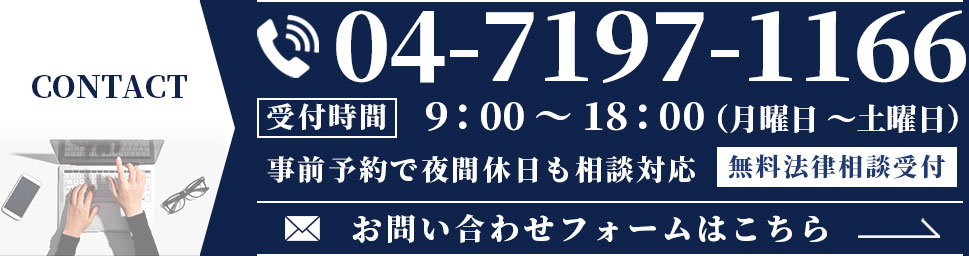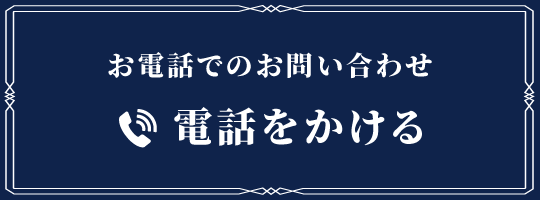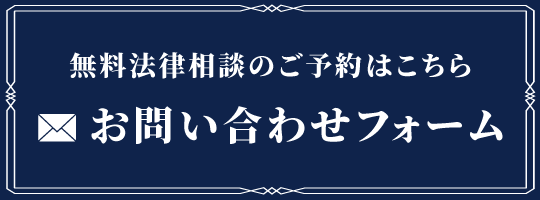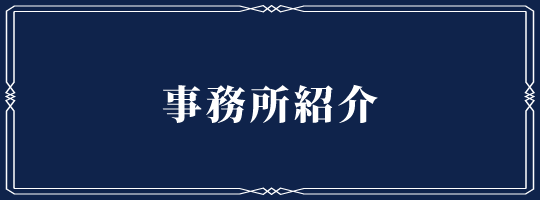遺言が無効となる事由について簡単に説明します。
なお、以下は一般的、代表的なものを記載したものであり、無効事由がこれに限られるというものではありません。
このページの目次
方式違背
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」(民法960条)と定められており、民法の定める一定の方式に従ってされることが必要となる要式行為です。
遺言者の意思表示が真意であることを明確にするために、方式に従ったものであることが求められています。
遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言といった種類ごとに、形式が定められており、これに従って作成される必要があります。
そして、方式に違背して作成された遺言は、無効となることがあります。
自筆証書遺言であれば、
- 全文の自書(例外有)
- 日付の自書
- 氏名の自書
- 押印
の要件を満たして作成する必要がありますが、文章が他人によって書かれたものである等、これらの方式に違背する場合に、無効とされることがあります。
公正証書遺言の場合でも、欠格事由がある者が証人になった場合(未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人)等、民法の規定に従わずに行われた遺言が無効となる場合があります。
遺言能力の欠如
民法961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」(民法961条)と定めており、15歳以上の者が、遺言をすることができるものとされています。
また、15歳以上であることに加えて、遺言を単独で有効に行いうる能力(遺言能力)が求められます。遺言能力とは、具体的には、遺言者が遺言事項(遺言の内容)を具体的に決定し、その法律効果を弁識するに必要な判断能力であると説明できます。
したがって、遺言能力がない者がした遺言は、遺言能力を欠くものとして無効となります。実務上は、認知症等で判断能力が低下していたことを理由に遺言能力が争われるケース等が見られます。
意思表示の瑕疵
遺言が、詐欺や強迫(民法96条1項)によって作成されたものである場合に、これを理由として遺言が取り消されれば、当該遺言は無効となります。
また、錯誤(民法95条)を理由として、遺言の効力を否定した裁判例もあります。
もっとも、上記のような意思表示の瑕疵を理由とする取消し(遺言の効力の否定)は、遺言者が死亡している以上、主張立証上のハードルが高いものとなります。
公序良俗違反
遺言の内容が、社会的妥当性を下記、公序良俗に違反する場合(民法90条)には、無効となります。
具体的には、不貞相手への関係維持を条件(目的)とする遺贈等が挙げられます。
もっとも、不貞関係にある者への遺贈が常に公序良俗違反により無効とされるものではなく、遺贈の目的や相続人に与える影響、夫婦関係といった様々な点を考慮して判断されることから、注意が必要です。
共同遺言
民法975条は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と規定しており、この規定に反して、同一の遺言証書で2人以上の者が遺言を行った場合には、当該遺言は無効となります。
同一証書での遺言を認めると、遺言の自由に支障をきたすこと、他の遺言との関係において効力が問題となりやすいこと、自由な撤回ができなくなることといった理由から設けられている規定と理解されています。
もっとも、形式的に2名以上の氏名が記載されていれば直ちに共同遺言となるというものではなく、遺言の形式や内容を踏まえて個別に判断する必要があります。
遺言の撤回
民法1022条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定しており、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言を撤回する自由を有することが定められています。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合や、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合についても、その抵触する部分については、撤回されたものとみなされます。
撤回された遺言は効力を失うことになります。