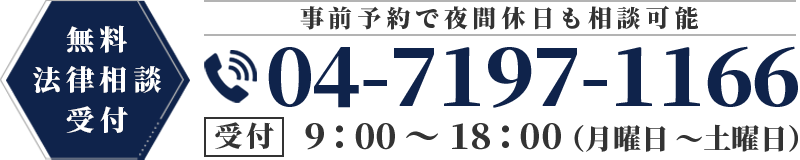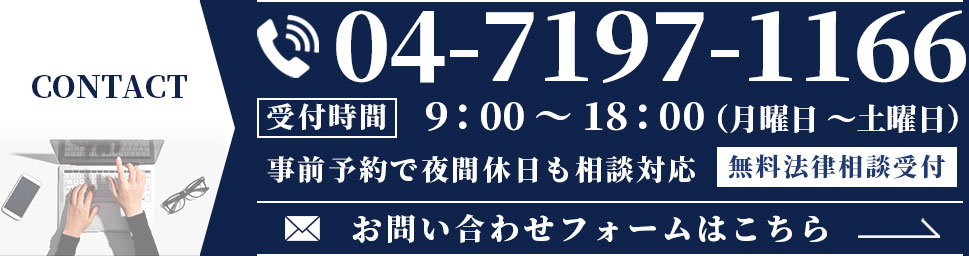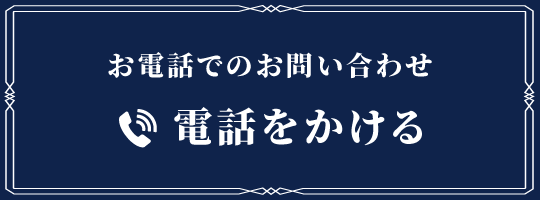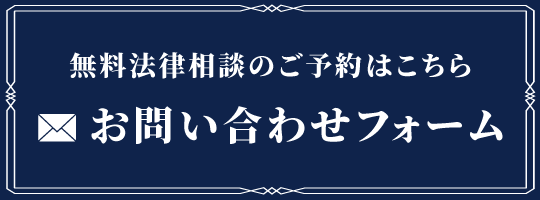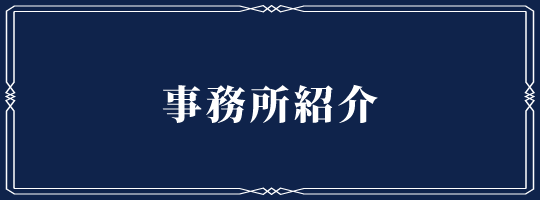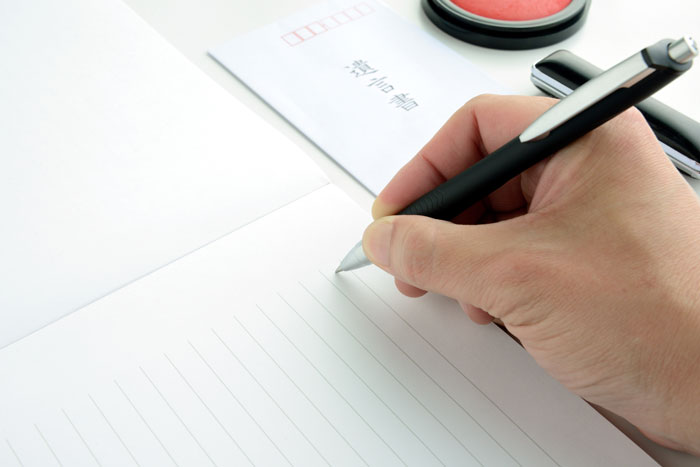
遺言は、亡くなった方(被相続人)のご意思を明確にするもので、遺産分割において重要な判断材料となるものです。しかし、遺言がある場合でも、それを巡って相続人の間でさまざまな問題が起こることがあります。
このページでは、遺言に関するよくあるトラブルや問題点、その対処法について詳しく解説いたします。
このページの目次
遺言とは
遺言とは、自身が亡くなった後の財産の分け方やその他の事項について、生前に自分の意思を表明しておくための法的な文書です。遺言書がある場合、原則として、その内容が優先され、遺言の内容にしたがって財産の帰属が定められます。
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」(民法960条)と定められており、民法の定める一定の方式に従ってされることが必要となる要式行為です。
遺言者の意思表示が真意であることを明確にするために、方式に従ったものであることが求められています。
そのため、単に口頭で行ったような場合等、民法の方式に従わずに行われたものは、民法の定める「遺言」としては効力を生じません。
遺言事項
遺言は、遺言者の死亡後にその効力が生じます(民法985条1項)。
そのため、遺言の効力が発生する時点では、遺言者は存在しないことから、遺言の内容の確定(遺言者の真意の確定)を巡っては、紛争が生じやすいものとなります。
そのため、民法では遺言をすることができる事項を限定しています。
下記が遺言をすることができる事項の一例となります。
- 認知(民法781条2項)
- 未成年後見人または未成年後見監督人の指定(民法839条、民法848条)
- 相続人の廃除または廃除の取消し(民法893条、民法894条)
- 祭祀に関する権利の承継者の指定(民法897条)
- 相続分の指定または指定委託(民法902条)
- 特別受益者の相続分の定め(民法903条)
- 遺産分割方法の指定または指定委託(民法908条)
- 相続開始の時から5年を超えない期間を定めての遺産分割の禁止(民法908条)
- 遺贈(民法964条)
- 遺言執行者の指定または指定委託(民法1006条)
- 保険金受取人の変更(保険法44条、73条)
遺言の種類
遺言の種類は、下記の7種類となります。
- 自筆証書遺言(民法968条)
- 公正証書遺言(民法969条)
- 秘密証書遺言(民法970条)
- 危急時遺言(民法976条)
- 伝染病隔離者遺言(民法977条)
- 在船者遺言(民法978条)
- 船舶遭難者遺言(民法979条)
遺言をめぐる問題が起きる代表的なケース
遺言を残していても、それが完全にトラブルを防げるわけではありません。
主に以下のようなケースで、問題が発生しがちです。
- 遺言の内容が不明瞭で理解できない
- 遺言書自体の有効性が疑わしい
- 一部の相続人だけに有利な遺言内容である
- 遺留分を侵害する遺言である
- 複数の異なる遺言書が発見された
具体的に起こり得る遺言トラブルとその内容
① 遺言書の「有効性」に関する問題
遺言には形式的な要件が法律で厳しく定められています。
例えば、自筆遺言では、一部の例外を除いて、全文・日付・署名のすべてが自筆でなければならず、パソコンで作成された遺言や代筆は原則認められません。また、公正証書遺言では、証人や公証人の立ち合いが義務付けられています。
これらの要件を満たさない遺言書は無効と判断される場合があります。
- 日付の記載が曖昧で、有効性が問われるケース
- 署名や押印がないため遺言書が無効になるケース
- 法的能力がない状態(認知症や好ましくない精神状態等)で遺言を書いた可能性が疑われるケース
② 遺言の内容が不明確で問題が発生するケース
遺言の内容が曖昧である場合、遺産分割ができないという問題が生じます。
例えば、「株式を妻に」、「自宅を長男に」としても、具体的な株式の特定や自宅の住所等が記載されていない場合、分割が曖昧になり、相続人間の争いにつながることもあります。
③ 遺留分をめぐる問題
一定の相続人(配偶者、子ども、親など)には、法律に定められた最低限の遺産を受け取る権利が保障されており、これを「遺留分」と呼びます。
しかし、遺言がこの遺留分を侵害してしまうケースが時折あります。
- 兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分がある
- 遺留分を侵害された相続人が、侵害を受けた財産を取り戻すため「遺留分侵害額請求」を行う場合がある
④ 複数の遺言が発見されるケース
遺言は新しい日付のものが有効であり、古い遺言書を撤回することが可能です。
しかし、複数の遺言書が見つかり、その内容が異なる場合、どれが有効なのかを巡り争いが発生します。
- 特に日付が不明瞭なケースや同日に作成された複数の遺言があるケースでは、特定が難しく裁判所での判断が必要になることもある
遺言に関する問題が起きた時の対処法
① 遺言書の「検認」手続きの活用
自筆で書かれた遺言書が自宅等で発見された場合は、速やかに家庭裁判所の「検認」手続きを利用しましょう。
「検認」とは遺言書の形式や内容を裁判所が確認・記録するための手続きで、有効性そのものは判断されませんが、偽造や改ざんなどを防ぐ効果があります。
自筆証書遺言の場合には、この手続きが必須です。
② 「遺留分侵害額請求」を検討する
遺言による財産分配が著しく不公平であったり、最低限の相続分(遺留分)を侵害されたと感じた場合には、「遺留分侵害額請求」の手続きを行うことができます。
侵害を知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内の請求期限があるため、注意が必要です。
③ 遺言無効確認を求める訴訟の利用
遺言書自体が疑わしい場合(偽造・変造・詐欺・強迫・認知症で判断能力がなかったなど)は、「遺言無効確認訴訟」によって遺言書の無効を裁判所に訴え、公平な判断を受けることも可能です。
ただし、証拠による立証が要求される訴訟のため、専門家のサポートが望ましいです。
遺言トラブルを未然に防ぐポイント
- 遺言はできるだけ公正証書遺言にて作成しておくこと
- 遺言内容を具体的に明確にしておくこと
- 家族間で遺言書の存在や内容を予め共有しておくこと(状況により配慮が必要)
- 遺言内容を定期的に見直す(書き直す)こと
まとめ
遺言に関わる問題は、その内容や遺言書の種類・形式によって対処法が複雑になるケースがあります。迅速かつ的確な対処法を選択することが大切ですが、一般の方が一人で取り組むことは難しい場合があります。
私たちの法律事務所では、遺言をめぐるトラブル解決や遺言書作成支援など、遺言に関するご相談に多くの実績を積んでおります。遺言トラブルでお困りの際は、お一人で悩まず、安心して当事務所までお気軽にご相談ください。