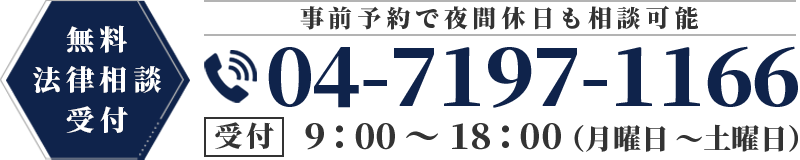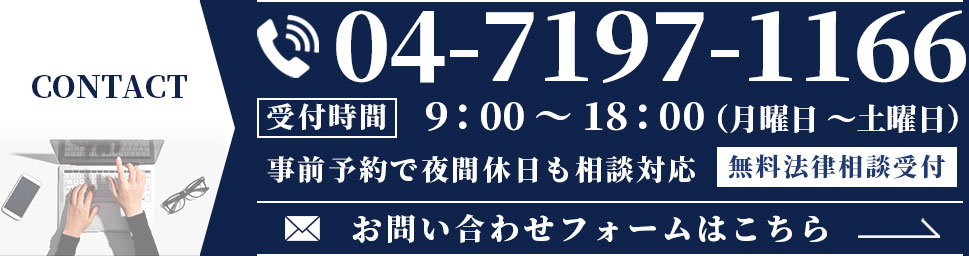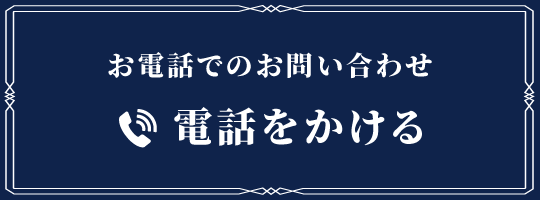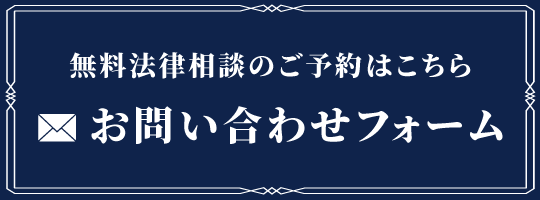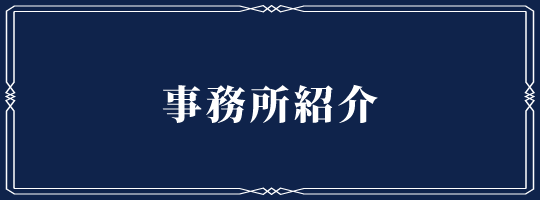遺言は、故人の大切な意思を示すものですが、実際にはその法的効力について疑問や不満が生じ、争いが発生するケースもあります。
「自分の知らない間に遺言が作成されていた」「一部の相続人のみが財産を取得する内容となっている」「遺言作成時の故人の判断能力に問題があった」という場合などでは、遺言の効力を巡るトラブルが起きがちです。
このページでは、そのような遺言の効力に関する争いが生じた際の法的対応方法について詳しくご説明いたします。
このページの目次
遺言の効力が問題になる具体的なケース
遺言の効力についての争いがよく生じる例として、以下のようなものがあります。
- 遺言作成時に判断能力(意思能力)に疑いがある場合(認知症、病気など)
- 遺言書の書式や要件に不備がある場合(署名・日付の欠如など)
- 偽造・変造された可能性がある場合
- 第三者による不当な働きかけ(脅迫・詐欺)があったと思われる場合
- 複数の異なる内容・日付が記された遺言書が見つかった場合
遺言の効力を巡る争いへの代表的な法的対応
遺言に関して問題が発生した際には、次のような法的手続きを検討・活用することが重要です。
① 遺言書検認の申立て
自筆証書遺言を見つけた場合には、争いの有無にかかわらず、家庭裁判所にすみやかに検認の申立てを行う必要があります(民法1004条3項)。
遺言の「検認」とは、遺言書が変造・偽造などされないように家庭裁判所で遺言の状態(筆跡・封印・日付)を調べ、その存在を正式に記録する手続きです。
検認はあくまでも遺言書の客観的状態に関する現状を確認し、証拠を保全する手続きであるため、遺言書の内容の法的有効性そのものが判断されるわけではありませんが、その内容を巡る争いの前提として非常に重要です。
遺言書を家庭裁判所で確認することにより、改ざんの防止や公正な手続きの確保が図られます。
② 遺言無効確認訴訟
遺言の効力をめぐる問題の中で、遺言の効力を争いたい場合に用いられる手続きが「遺言無効確認訴訟」です。この訴訟は、遺言自体の法的効力を全面的に裁判所に判断してもらうための手段です。
具体的には以下のような状況で訴訟の提起が検討されます。
- 故人が遺言書作成当時、認知症や病気などで遺言作成に必要な判断能力がなかった疑いがある場合
- 第三者による強迫、詐欺などが存在した疑いがある場合
- 遺言書が偽造または改ざんされている可能性が高い場合
- 遺言書の作成方法・形式(署名・日付・押印)が法律で定める要件を満たしていない場合
手続き・期間
遺言無効確認訴訟は家庭裁判所ではなく、地方裁判所に申し立てることになります。
この訴訟には明確な期限はありませんが、証拠の鮮明さや他の相続人との関係も考慮し、早めの対応を行うことが望ましいとされています。所要期間はケースにもよりますが、1年以上要することも多くあります。
③ 遺留分侵害額請求
遺言書自体に問題がなくても、その内容が法律に定められた一定の相続人(配偶者・子ども・直系尊属)の最低限の取り分(遺留分)を侵害している場合には、「遺留分侵害額請求」を行い、不利益を是正する方法があります。
- 遺留分侵害額請求の期限は、遺留分侵害の事実を知った日から1年以内、遺言者の相続開始から10年以内です。この期限を過ぎると請求できなくなりますので、注意しましょう。
- 通常は裁判外で通知・交渉を開始し、任意解決が難しい場合は裁判所の調停や裁判手続きを通じて問題を解決します。
遺言の効力を争う場合の手続き一覧と期間目安
| 対応手続き | 申立て先 | 主な申立て理由・根拠 | 期間の目安 (遺留分は期限) |
| 検認の申立て | 家庭裁判所 | 自筆証書遺言の発見時 | 申立て後1~2か月以内に行われることが多い |
| 遺言無効確認訴訟 | 地方裁判所 | 意思能力欠如・偽造・脅迫・手続き違反などが疑われる場合 | 数ヶ月~1年以上 |
| 遺留分侵害額請求 | 通常は裁判外、場合により家庭裁判所で調停・訴訟 | 法定の遺留分が侵害された場合 | 侵害の事実を把握後1年以内、または相続開始後10年以内 |
遺言の効力を争う際に注意すべきポイント
- 速やかに証拠収集・保全を行う(遺言書の原本・診断書・介護施設や病院での記録、関係者の証言など)
- 感情的にならず、相続人間の良好な関係にも配慮した進め方を検討する
- 各法律手続きの期限を厳守する
- 専門家である弁護士に早めに相談し、適切なアドバイスを受ける
まとめ
遺言の法的効力を争う手続きは、法的知識や経験が豊富な弁護士に依頼されることをおすすめします。当法律事務所では、遺言無効訴訟、遺留分侵害額請求をはじめとした相続に関するご相談・解決実績が豊富です。
遺言の効力に関する争いに直面された場合は、ご自身だけで悩まず、ぜひ専門家である弁護士までお気軽にご相談ください。迅速かつ丁寧に解決に向けてサポートをさせていただきます。