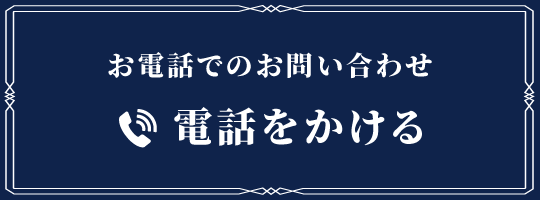このページの目次
遺言の方式
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」(民法960条)と定められており、民法の定める一定の方式に従ってされることが必要となる要式行為です。
遺言者の意思表示が真意であることを明確にするために、方式に従ったものであることが求められています。
そのため、単に口頭で行ったような場合等、民法の方式に従わずに行われたものは、民法の定める「遺言」としては効力を生じません。
遺言能力
① 遺言能力
「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」(民法961条)と定められており、民法は、15歳に達した者について、遺言をすることができるものとしています。
遺言能力については、遺言を単独で有効に行いうる能力であると理解されていますが、具体的には、遺言者が遺言事項(遺言の内容)を具体的に決定し、その法律効果を弁識するに必要な判断能力であると説明できます。
一般には、行為能力よりは低い程度の能力で足りるものと理解されています。
当然ながら意思能力は求められるため、遺言者が遺言時に意思能力を欠いていた場合には、遺言は無効となります(民法3条の2)。
なお、遺言能力を有していたか否かの判断に当たっては、遺言の内容やその難易との関係で相対的に判断されることになります。
② 制限行為能力者に関する規定の不適用
民法962条は、「第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。」と定めており、未成年者や制限行為能力者であっても、有効に遺言をすることができます。
未成年者であっても、親権者や未成年後見人の同意がなくても遺言をすることができ、成年被後見人がした遺言であっても、意思能力を欠いていなければ、成年後見人がこれを取り消すことはできません。
もっとも、成年被後見人については、事理弁識能力を欠く常況にあるものであるため、事理弁識能力を一時回復したときにおいて遺言をするためには、医師二人以上の立会いが必要です(民法973条1項)。
被保佐人や被補助人も、保佐人または補助人の同意を得ずに遺言をすることができます。
③ 遺言能力が求められる時点
民法963条は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定めています。
つまり、遺言能力が求められる時点は、遺言をする時となります。遺言をした時点で、遺言能力を有していた場合には、その後遺言能力を喪失した場合であっても、これを理由に遺言が無効となることはありません。
遺言事項
遺言は、遺言者の死亡後にその効力が生じます(民法985条1項)。
そのため、遺言の効力が発生する時点では、遺言者は存在しないことから、遺言の内容の確定(遺言者の真意の確定)を巡っては、紛争が生じやすいものとなります。
そのため、民法では遺言をすることができる事項を限定しています。
下記が遺言をすることができる事項の一例となります。
- 認知(民法781条2項)
- 未成年後見人または未成年後見監督人の指定(民法839条、民法848条)
- 相続人の廃除または廃除の取消し(民法893条、民法894条)
- 祭祀に関する権利の承継者の指定(民法897条)
- 相続分の指定または指定委託(民法902条)
- 特別受益者の相続分の定め(民法903条)
- 遺産分割方法の指定または指定委託(民法908条)
- 相続開始の時から5年を超えない期間を定めての遺産分割の禁止(民法908条)
- 遺贈(民法964条)
- 遺言執行者の指定または指定委託(民法1006条)
- 保険金受取人の変更(保険法44条、73条)
遺言の種類
遺言の方式としては、下記の7種類となります。
- 自筆証書遺言(民法968条)
- 公正証書遺言(民法969条)
- 秘密証書遺言(民法970条)
- 危急時遺言(民法976条)
- 伝染病隔離者遺言(民法977条)
- 在船者遺言(民法978条)
- 船舶遭難者遺言(民法979条)