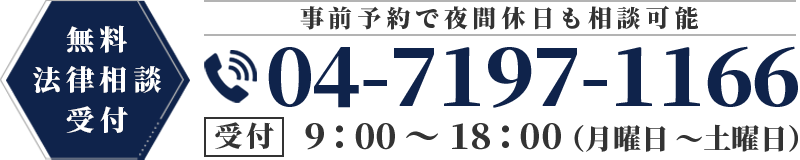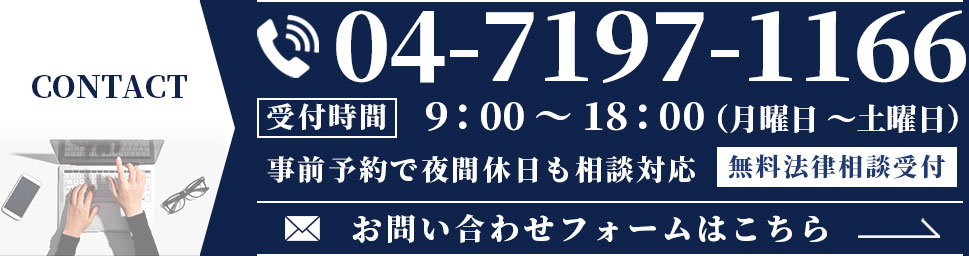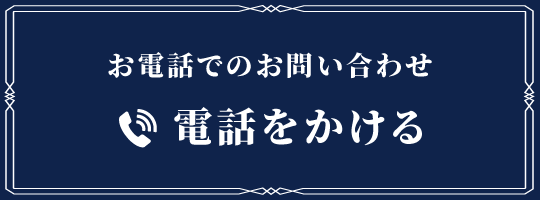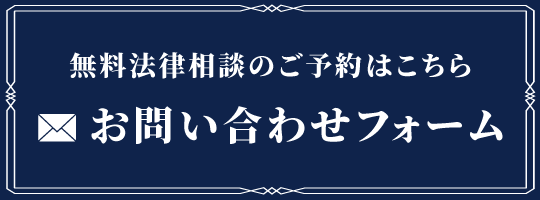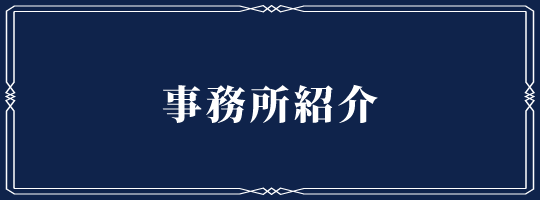相続手続きを円滑に進めるためには、まずは「相続財産調査」を行うことが重要です。
相続財産調査では、故人(被相続人)が遺した資産や負債を正確に把握します。この調査が正確に行われることで、その後の遺産分割協議や相続税申告においてトラブルを避けることができます。
本稿では相続財産調査の基本的知識と金融機関からの残高証明書取得方法について、具体的に詳しくご説明いたします。
このページの目次
相続財産調査とは?目的と重要性
相続財産調査とは、被相続人が保有していた財産内容を詳しく調査することです。主に次の財産を調査し、その状況を把握します。
- 預貯金、現金
- 不動産(土地・建物など)
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 生命保険金・退職金(みなし相続財産含む)
- 借入金・借金などの負債
こうした調査は、相続税の申告や遺産分割協議を正確・円滑に進めるために欠かせません。また、負債を把握せず相続してしまうと、後に問題となる場合もあります。
相続財産調査を正確に行うことで、不要なトラブルのリスクを大きく軽減できます。
相続財産調査の具体的な進め方と注意点
相続財産調査の手順はおおよそ以下のようになります。
① 保有資産の把握
- 金融機関の口座調査(銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫など)
- 不動産資産の調査(登記事項証明書取得、固定資産評価証明書取得)
- 有価証券調査(株式・証券会社との取引確認)
- 生命保険金の調査(生命保険会社への確認)
- その他資産の確認(貸金庫、貴金属、会員権など)

② 負債の把握
- 金融機関のローン残高や借入金の調査
- クレジットカードや消費者金融の利用履歴の調査
- 個人的な借金、連帯保証債務の把握
注意点は、後から新たな資産や負債の発覚がないよう、被相続人の郵便物や保管資料を細かく確認することです。
残高証明書とは?その役割について
残高証明書とは、金融機関に存在する預貯金やローンなどの口座の残高を証明する公式な書類です。
相続財産調査においては、預金などの金融資産の確認として欠かせない重要資料です。そのため、通常は各金融機関から相続発生日の残高証明書を取得します。
残高証明書が必要な理由
- 相続税申告の際に正確な財産状況を証明するため
- 遺産分割協議の際に資産を公平かつ正確に分割する根拠資料とするため
残高証明書取得の具体的な手続き方法
残高証明書は金融機関へ依頼し発行手続きを行います。
具体的な方法は下記のような手順で進めます。
① 金融機関の支店または窓口での手続き
必要書類を持参して口座開設支店へ直接出向き、手続きを行います。

② 必要書類と手数料
各金融機関により異なる部分もありますが、一般的に以下の書類が必要です。
実際の手続きに際しては、各金融機関に個別にお問い合わせください。
- 故人の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本も可)
- 手続きをする相続人自身の戸籍謄本
- 相続人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書)
- 残高証明書発行依頼書(各金融機関指定の様式、金融機関のホームページ等で入手可能)
- 手数料(一部無料の金融機関もありますが、通常1通あたり500円〜1,000円程度)
※残高証明書依頼の際、相続発生日時点の証明を取得する必要があるため、発行依頼書の「基準日」を「被相続人の死亡日」に設定することがポイントです。

③ 郵送による申請も可能
遠方や忙しくて直接窓口に出向くのが難しい場合でも、多くの金融機関では郵送による取得も可能です。
その際は、必要書類一覧の提出や返信用封筒と切手を同封するのを忘れないよう注意しましょう。
相続財産調査と残高証明書取得を専門家に依頼するメリット
相続財産調査は細かく手間がかかる作業であり、多くの相続人にとって負担になることがよくあります。専門家(弁護士等)に依頼するメリットとして主に次のようなものがあります。
- 調査漏れや間違いを防ぎ、正確な相続財産の把握が可能
- 短期間で迅速に調査を完了できる
- 残高証明書の取得依頼や各種連絡をプロがまとめて行うことで、相続人の手間や負担が大きく軽減される
当事務所では、多数の相続案件を取り扱った経験を活かし、相続財産調査から残高証明書取得までを全面的にサポートしています。
まとめ
相続財産調査と残高証明書の取得は、相続手続きにおいて欠かせないステップです。正確かつ迅速な調査を行うことにより、遺産分割や相続税申告などその後の過程がスムーズに行えます。
調査に不安がある場合や時間的に余裕がない方は、当事務所のような相続に詳しい専門家にお気軽にご相談ください。皆様の相続手続きをしっかりと、丁寧にサポートさせていただきます。