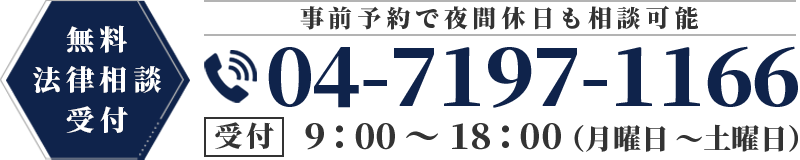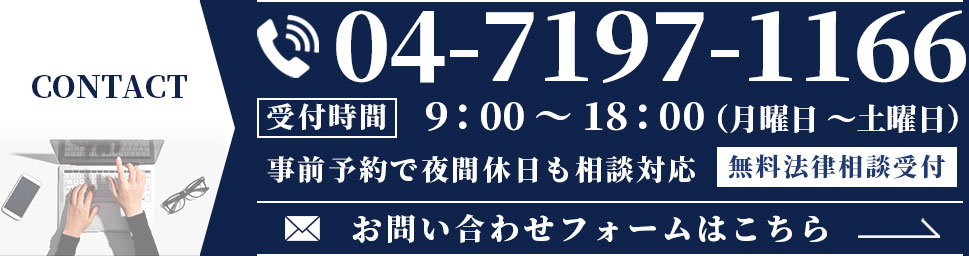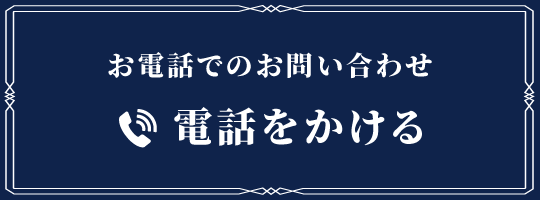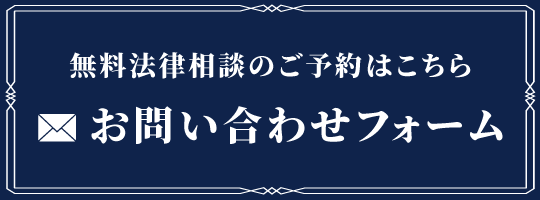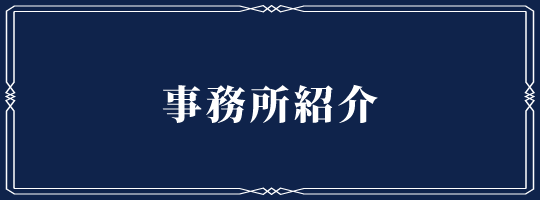相続手続きにおいて必ず必要となるのが、相続人の関係性を明確に示した書面である「相続関係説明図」です。
聞き慣れない方も多いかもしれませんが、この相続関係説明図を適切に作成することで、多くの相続手続きをスムーズに進めることが可能になります。
今回は、相続関係説明図の作成方法や、実際のメリットについてわかりやすく解説いたします。
このページの目次
相続関係説明図とは何か?
相続関係説明図とは、亡くなられた方(被相続人)と相続人との関係性をひと目で分かるように図式化した書類です。
法務局で不動産などの名義変更(相続登記)をする際などに求められる重要書類の一つです。
相続関係説明図の主な特徴
- 被相続人を中心として、相続人との関係を分かりやすく表現した書類
- 戸籍謄本や除籍謄本等の証明書を基に作成します
- 相続登記をする際、複数の役所・機関へ提出する戸籍関係の書類を簡略化する役割があります
相続関係説明図を作成するメリットとは?
相続関係説明図を作成することには以下のメリットがあります。
- 相続手続きが効率的に進められる
法務局や金融機関等へ提出する戸籍資料と一緒に相続関係説明図を提出することで、戸籍類の原本を返却してもらえる場合があり、手続きが迅速かつ簡単になります。 - 相続人関係を明確にできる
見やすく整理された図により、関係機関との意思疎通がスムーズになります。遺産分割協議の際にもトラブルを防げる場合があります。 - 相続手続きの際の負担軽減
戸籍関係書類を複数用意する必要がなくなる場合があり、書類取得の手間や費用を減らすことが可能です。
相続関係説明図の作成手順を分かりやすく解説
ここからは実際に相続関係説明図を作成する具体的な方法についてご紹介いたします。
① 必要な戸籍等の書類を収集する
相続関係説明図を作成するためには以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本
- 相続人(配偶者・子供・父母・兄弟姉妹など)の現在の戸籍謄本
これらの書類は市区町村役場で取得できます。書類取得について疑問がある場合は、法律事務所などの専門家への相談もおすすめです。

② 相続関係説明図の基本的な構成を理解する
相続関係説明図は、通常被相続人を一番左側に記載し、そこから右方に相続人へと枝分かれする形式で示します。
主な記載事項は以下の通りです。
- 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日
- 相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄
- 作成した日付と作成者の氏名・住所(最下部に記載)

③ 実際に相続関係説明図を作成する
必要な戸籍を参考に、以下のような形式で図を書きましょう。手書きでも問題ありませんが、なるべく見やすく、分かりやすく書くことが重要です。
(相続関係説明図の書き方の一例)
- 左端に『被相続人 山田太郎(昭和20年1月1日生、令和5年3月10日死亡)』と記載
- 被相続人から右方向に線を伸ばし、相続人を記載(配偶者・子供など)
- 各相続人の氏名、生年月日、続柄を明記する

④ 作成後の相続関係説明図の提出・利用方法
完成した相続関係説明図は、相続登記の申請をはじめ、金融機関での口座解約、遺産分割協議の資料としても利用できます。