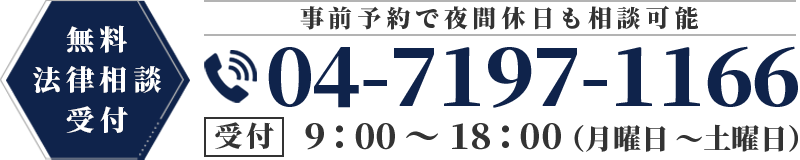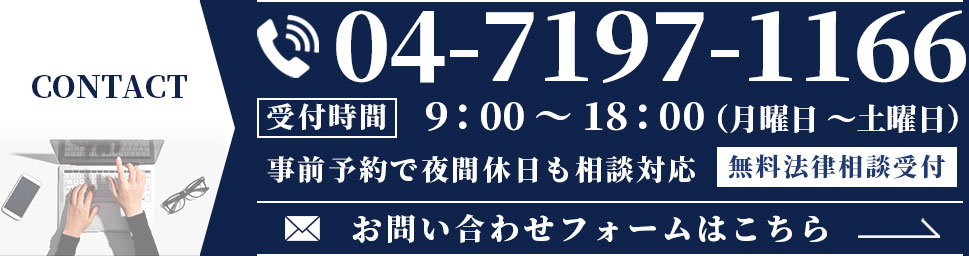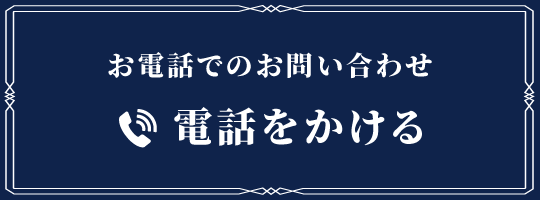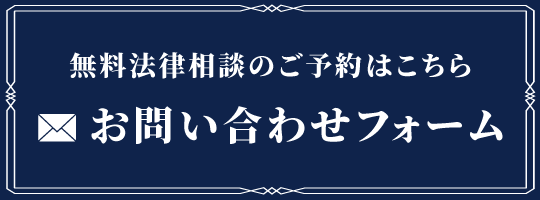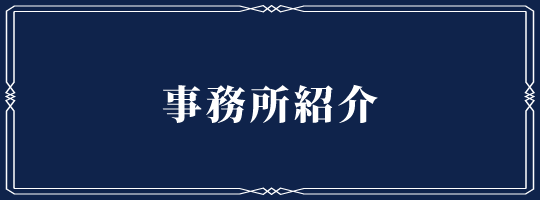このページの目次
寄与分とは
民法904条の2第1項は、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」と規定しており、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人がいる場合には、みなし相続財産の額及び具体的相続分の算定に影響を与える旨が定められています。
寄与分は、相続人間の公平を図る制度ですが、同趣旨のほか、被相続人との関係での清算の実現という面もあるものと考えられています。
寄与分が認められる場合の算定方法
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと認められる共同相続人がいる場合、①みなし相続財産は、相続開始時の財産から寄与分を控除して算定し、②共同相続人の具体的相続分の算定に当たっては、当該寄与分を加算して算定することになります。
以下、具体例を見ていきます。
具体例
① 想定するケース
以下では、
- 被相続人がA、相続人が夫B、子C及び子D
- 死亡時の遺産が3,000万円
- 夫Bの寄与分が1,000万円
というケースを想定します。
② みなし相続財産
みなし相続財産は、死亡時の遺産3,000万円から、寄与分である1,000万円を控除した2,000万円となります。
③ 具体的相続分
まず、各人について、みなし相続財産を法定相続分で分けると、
B=2,000万円×1/2=1,000万円
C=2,000万円×1/4=500万円
D=2,000万円×1/4=500万円
となります。
そして、Aについては、寄与分である1,000万円がここに加算されますので、Aの具体的相続分は、1,000万円+1,000万円=2,000万円となります。
したがって、具体的相続分は、
B=2,000万円
C=500万円
D=500万円
となります。
寄与分が認められる場合
① 「共同相続人による」特別の寄与行為
条文上、寄与行為は共同相続人によるものであることが定められており(904条の2第1項は、「共同相続人中に、(中略)特別の寄与をした者があるときは、」としており、共同相続人であることを前提としています。)、相続人以外の者により、被相続人の財産の維持又は増加に対し特別の貢献がされたとしても、基本的には寄与分として認められるものではありません。
もっとも、共同相続人以外の者の寄与が共同相続人の履行補助者による寄与と評価できるような場合には、当該共同相続人による寄与と評価されます。
裁判例(東京高決平成22年9月13日家月63巻6号82頁)においても、共同相続人の妻による被相続人の看護を、「同居の親族の扶養義務の範囲を超え,相続財産の維持に貢献した側面があると評価することが相当である。」としたうえで、同人による「被相続人の介護は、抗告人(共同相続人)の履行補助者として相続財産の維持に貢献したものと評価できる」として共同相続人に寄与分を認めました。
なお、民法改正により、相続人以外の行為者による寄与であっても、特別寄与料(民法第1050条)として、相続人に対し、請求することができる場合が定められました。
また、少し細かい話になりますが、相続人が、相続人の地位を得る前に被相続人に対して寄与行為を行った場合に、これが寄与分として認められるかという議論もあり、認められるとする見解と認められないとする見解に分かれています。
② 特別の寄与行為
特別の寄与とは
「特別の寄与」とは、被相続人と相続人との身分関係に基づいて行うことが通常期待される程度を超える特別の貢献であると理解されています(最高裁判所事務総局家庭局「改正民法及び家事審判法規の解釈運用について」家月33巻4号)。
判断要素
東京家庭裁判所家事第5部が示している資料「寄与分の主張を検討する皆様へ」によると、寄与分が認められるための要件として、「その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠であったこと」、「特別な貢献であること」、「被相続人から対価を得ていないこと」、「寄与行為が一定の期間あること」、「片手間でなくかなりの負担を要していること」、「寄与行為と被相続人の財産の維持または増加に因果関係が認められること」が挙げられています。
全てを「要件」としているように読めますが、実際は、下記類型ごとに要件とされるものは異なるものと考えられます。
実際に、東京家庭裁判所家事第5部が示している資料においても、寄与の類型ごとに要素が分けて挙げられています。
特別な寄与の判断要素
特別性
前述のように、特別な寄与とされるためには、被相続人と相続人との身分関係に基づいて行うことが通常期待される程度を超える特別の貢献である必要があります。
もっとも、どの程度の貢献が「通常期待される」ものであるかについては、被相続人と共同相続人との間の身分関係や生活関係によって異なります。
夫婦や親子は、夫婦間の扶助義務(民法第752条・同第760条)、親族間の相互扶養義務(民法第877条)を負っているため、同義務の範囲内の義務を履行した程度であれば、特別性が認められません。
無償性
- 対価を受け取っている場合
共同相続人(寄与者)が、被相続人から行為に対して相当の対価を得ていた場合には、同行為は無償の寄与ではなく、寄与分とは評価されません。
この点について、被相続人が経営する簡易郵便局の事業に従事したとして、寄与分が主張された事案で、「(相続人が)月25万円から35万円という相応の収入を得ていたことが認められること、(相続人が)被相続人と同居し,家賃や食費は被相続人が支出していたこと」を考慮して、「上記郵便局の事業に従事したことにより相応の給与を得ていたというべき」であるとして、特別受益と評価されないものと判断した裁判例(札幌高決平成27年7月28日判タ1423号193頁)があります。 - 生前贈与や遺贈を受けている場合
共同相続人(寄与者)が、寄与行為に対する対価の趣旨で生前贈与や遺贈を受けている場合にも、それによって、寄与行為が評価され尽くされている場合には、寄与分とは認められないものと考えられます。
なお、細かい話になりますが、この場合(寄与行為に対する対価として被相続人から共同相続人への生前贈与が行われている場合)に当該生前贈与は、共同相続人の特別受益として認められるのかという問題が別途生じます。
この点については、当該生前贈与について持戻し免除を認めるといった対応が考えられます。
特別受益について、共同相続人への贈与は、長年にわたる妻としての貢献に報い、その老後の生活の安定を図るためにしたものであるとして、黙示の持戻し免除の意思表示を認め、他方で、寄与分については、「長年にわたる貢献をしてきた事実は認められるが、上記の贈与によって共同相続人(寄与者)が得た利益を超える寄与があった事実は認めることができない」としてこれを否定した裁判例(東京高決平成8年8月26日家月49巻4号52頁)が参考になります。
継続性
寄与行為の態様によっては、当該寄与行為の提供が一定期間継続されていることが求められるものがあります。
一般的には、寄与行為の態様が、被相続人の事業に関する労務の提供、療養看護、扶養及び財産管理の場合において求められます。他方で、寄与行為の態様が財産給付であるような場合には、この要素が必要となるものではありません。
専従性
一般的には、寄与行為の態様が、被相続人の事業に関する労務の提供、療養看護の場合において求められます。
なお、ここでの専従性は、厳密に専業というところまでが求められるものではなく、片手間ではないという程度の専従性で足りるものと考えられています。
特別の寄与の類型
被相続人の事業に関する労務の提供(家事従事型)
共同相続人が、被相続人の事業に対して労務の提供を行ったような場合です。
上記要件との関係では、
- 特別な貢献であること
- 無償であること(無報酬や対価とは認められない低額な費用であること)
- 一定期間継続して行われていること
- 片手間ではなくかなりの負担を要していること
等が求められます。
被相続人の事業に関する財産上の給付(金銭等出資型)
共同相続人が、被相続人の営む事業に対して事業のための資金の提供等財産上の給付を行った場合です。事業により生じた債務の弁済も含まれます。
上記要件との関係では、①、②が求められます。一回の給付であっても認められ、性質上片手間か否かが問題となるものではない為、③及び④については、要件とならないものと考えられます。
療養看護
共同相続人が、疾病のある被相続人の療養看護を行った場合です。障害のある場合も含まれます。また、介護も含まれます。
上記要件との関係では、①、②、③及び④に加えて、⑤被相続人にとって必要であったことも求められます。
その他
- 金銭出資
共同相続人が、被相続人に対して財産上の利益の給付を行った場合です。
上記要件との関係では、①、②が求められます。 - 扶養
共同相続人が、被相続人を扶養或いは扶養料を負担したような場合です。夫婦や親子は、夫婦間の扶助義務(民法第752条・同第760条)、親族間の相互扶養義務(民法第877条)を負っているため、これを踏まえて、扶養が通常期待される以上のものか否かが問題となります。
上記要件との関係では、①、②、③、④及び⑤が求められます。 - 財産管理
共同相続人が、被相続人の財産管理を行った場合です。収益不動産の管理等が挙げられます。「管理」とありますが、所有不動産の売却等への関与についても、認められるケースもあります。
上記要件との関係では、①、②、③及び⑤が求められます。
寄与行為によって、被相続人の財産が維持又は増加したこと
寄与分は、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」に認められるものですので、被相続人の財産に維持または増加が要件となります。
また、寄与行為と被相続人の財産に維持または増加の間に因果関係があることも要件となります。
例えば、療養看護によって、被相続人を身体的・精神的には支えたような場合であっても、これが被相続人の財産の維持または増加させたものでなければ、寄与分として認められないことになります。
療養看護を行ったことにより、医療費及び看護費の支出を免れたというような場合(財産減少を防いだ場合)にも、財産の維持への寄与は認められます。もっとも、前提として、そのような療養看護が、特別な寄与(被相続人との身分関係に基づいて行うことが通常期待される程度を超える特別の貢献)と認められるか否かは、別途問題となります。
寄与分と生前贈与
被相続人から共同相続人への生前贈与が、寄与行為に対する実質的な対価として行われているようなケースでは、その限度で寄与分の請求はできないものとされます。
寄与分と遺贈
寄与分は、「被相続人が相続開始時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」(民法904条の2第3項)とされています。
その為、例えば、相続財産の全てが他の相続人に遺贈された場合には寄与分を主張することはできません。これは、相続させる旨の遺言の場合も同様です。
寄与分と遺留分
① 遺留分を侵害するような寄与分の定めについて
条文上は、特段、他の共同相続人の遺留分を侵害するような寄与分の定めを否定する規定はないことから、遺留分を侵害する寄与分を定めること自体は可能です。
しかしながら、実務上は、共同相続人の遺留分を考慮しつつ、寄与分を定めることが一般的です。
② 遺留分侵害額の算定における寄与分について
遺留分侵害額の算定について規定する条文(民法1043条から1046条)において、寄与分に関する規定は、準用されておらず、遺留分侵害額の算定に当たっては、寄与分は考慮されないものと考えられています。