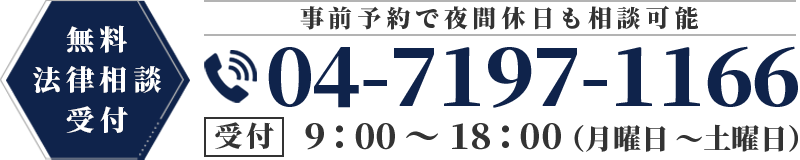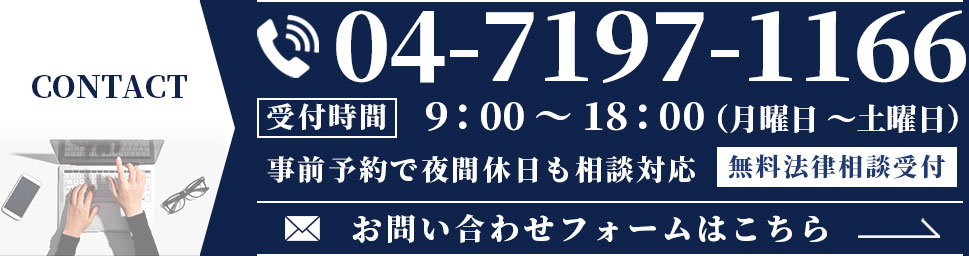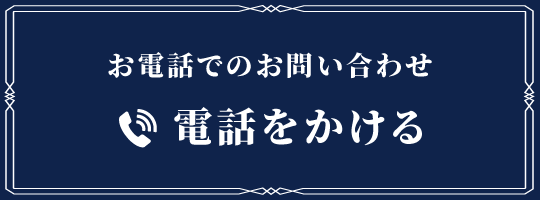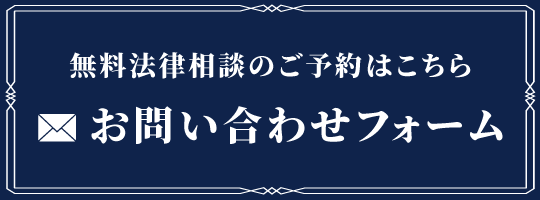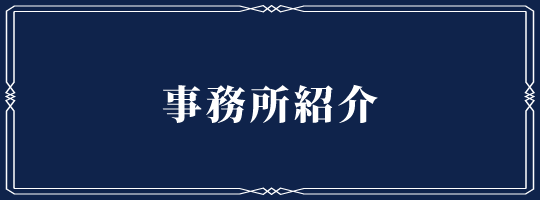家族が亡くなった際に、遺言書や生前贈与によって遺産の分け方が偏ってしまった場合でも、法律では一定の相続人に対し「遺留分」という最低限保障されている相続の権利が認められています。
自分が遺留分を侵害されている場合、遺留分侵害額請求という形で、他の相続人や遺贈を受けた人へ請求することができます。
ここでは、遺留分侵害額請求を行う際の具体的な手順について、分かりやすく詳しくお伝えします。
このページの目次
遺留分とは何か?対象となる相続人とは?
「遺留分」とは、法律(民法)で定められた相続人(配偶者、子ども、直系尊属など)が最低限確保できる財産の割合のことです。
これにより、相続人の最低限の生活や権利が保護されています。
遺留分の割合の一例
| 相続人の種類 | 遺留分の割合 |
| 配偶者または子ども | 法定相続分の1/2 |
| 父母(直系尊属)のみ | 法定相続分の1/3 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分はありません |
この割合に従い、相続財産総額から侵害されている金額を計算し、相手に請求することになります。
遺留分侵害額請求の対象となる事例
遺留分の侵害が発生するのは主に次のような場合です。
- 「特定の1人に全財産を相続させる」などの遺言がある。
- 一部の相続人や第三者に、生前贈与として大きな財産が渡されている。
- 再婚家庭など家族関係が複雑で、財産配分が偏っている。
遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れと方法
① 遺産内容の調査と把握
まず、相続財産の正確な内容と評価額を調査・把握する必要があります。不動産、預貯金、株式、生命保険金など、相続財産の種類はさまざまです。
財産の評価は専門性を要するため、専門家への相談がおすすめです。

② 遺留分侵害の金額の計算
財産総額が判明したら、自分が本来受け取るべき遺留分の割合を適用して、侵害された遺留分の金額を具体的に算出します。
この作業は専門家の適切な支援を受けることでスムーズに進められます。

③ 相手方への請求(内容証明郵便を利用)
遺留分侵害額請求を行う際には、通常、内容証明郵便を利用して請求します。内容証明郵便とは、送付した文書の内容や日時を郵便局が公的に証明してくれる制度で、後日のトラブル防止に役立ちます。
- 記載すべき主な項目は、請求者・相手方の氏名や住所、侵害額の算定根拠、請求金額、支払期限などです。
- 相続発生と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内に請求する必要があります。ただし、請求できる最終期限は相続開始時から10年です。

④ 協議・交渉による解決
相手方からの回答をもとに、侵害額について合意を目指す交渉が始まります。
金額だけでなく、支払い方法や期限についても、お互いに納得できるように協議します。

⑤ 家庭裁判所による調停や訴訟での解決(交渉困難な場合)
話し合いによる解決が難航した場合や相手方から返答がない場合、家庭裁判所での調停や訴訟手続きを申し立てることも可能です。調停や訴訟では、裁判官や調停委員が第三者として冷静に双方の主張を整理し、公平に仲裁します。
なお、交渉をせずに、いきなり調停を申し立てることも可能ですが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示とはならないものと考えられているため、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
遺留分侵害額請求手続きにおける注意点
- 「遺留分侵害額請求権」は、「相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年」と「相続開始から10年」という期間制限が設定されているため迅速な対応が求められます。
- 遺産評価ミスにより請求金額を誤ってしまうことのないよう、専門家に調査、計算を依頼することが極めて重要です。
- 不動産など評価の難しい財産が関係する場合は、各分野の専門家(法律、税務、不動産鑑定士)との連携が重要となります。
弁護士による支援を受けるメリット
遺留分侵害額請求に関する手続きは専門的で煩雑なため、弁護士へ依頼することがおすすめです。弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 相続財産調査、適切な遺留分計算を代行し、請求漏れを防ぐ。
- 相手方との感情的な対立を避け、冷静な交渉・協議を進める。
- 交渉難航時には裁判手続き(調停・訴訟)まで一括して対応できるため、安心です。
当事務所における遺留分侵害額請求サポートサービス
遺留分侵害額請求を検討しているお客様へ、当事務所では以下のようなサービスを親身に提供しております。
- 遺産内容の適正な評価・計算
- 内容証明郵便作成・発送手続き
- 相手方との交渉・協議での代理人
- 調停・訴訟手続きを含めた裁判所対応
まとめ
遺留分侵害額請求の手続きは複雑で期限もあります。そのため、早期から弁護士に相談し、適切な援助を得ることが重要です。
当事務所は相続問題において豊富な経験と実績がありますので、遺留分侵害額請求について不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。