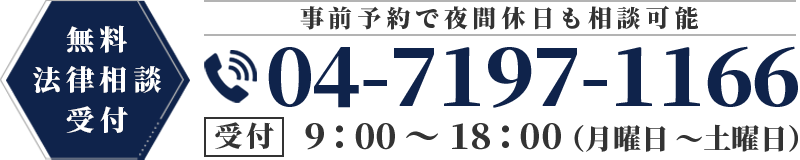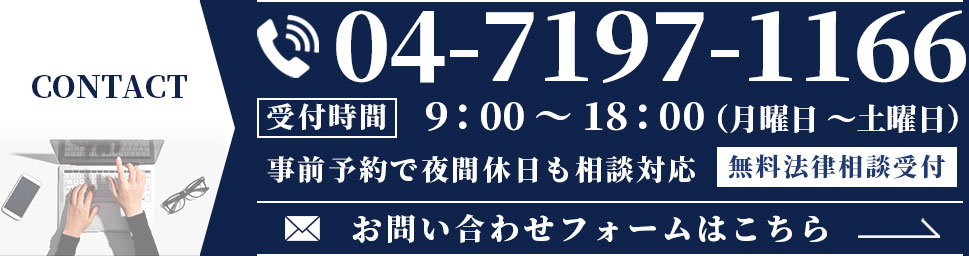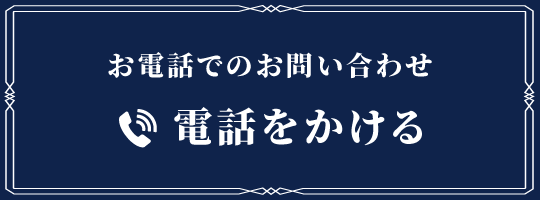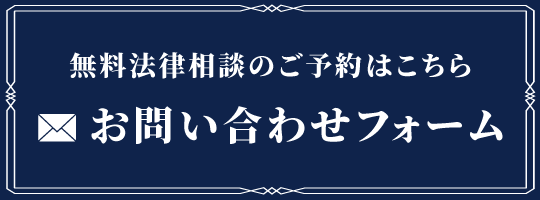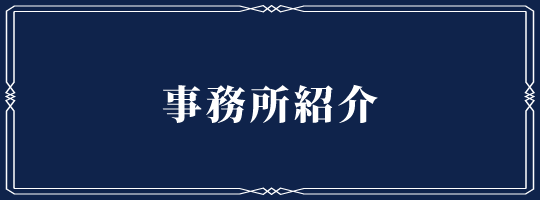遺産相続に関して、大切なご家族が残した遺言により受け取れるはずの財産が減ってしまったり、生前の贈与が他の相続人に偏っていたりする場合があります。
こうした状況にある方は、「遺留分侵害額請求」を行うことで、自分が得られる最低限の遺産を取り戻すことができます。
今回は、遺留分侵害額請求の計算方法の大枠と注意すべきポイントを簡潔に解説いたします。
このページの目次
遺留分侵害額請求とはそもそも何か?
「遺留分」とは、端的に説明すると、法律が一定の相続人(配偶者、子ども、両親など)に保障している最低限の取り分のことです。
この遺留分が侵害されてしまった場合に、自分の権利を主張して不足分の財産を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分が認められる相続人と割合
| 相続人の範囲 | 遺留分の割合 |
| 配偶者のみ、または子どものみ | 法定相続分の2分の1 |
| 配偶者と子ども | 各自の法定相続分の2分の1ずつ |
| 直系尊属(両親や祖父母)のみ | 法定相続分の3分の1 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし |
※兄弟姉妹には遺留分がありませんので、注意しましょう。
遺留分侵害額の計算方法について
遺留分侵害額の計算は、次のようなステップで進めます。
① 相続財産の総額を把握する
まずは亡くなられた方(被相続人)の遺産を正確に調査し、その総額を把握します。このとき、相続発生時点(死亡時)の評価額に基づいて財産の価値を調べます。不動産については固定資産税評価額や相場価格を参考に評価を行います。
遺贈の目的物となったものや、特定財産承継遺言(民法1047条1項)によって処分された財産についても、ここにいう積極財産に含まれるものと理解されています。

② 生前贈与の財産を加算する
相続財産の総額に加えて、亡くなった方が生前に行った一定期間内の贈与財産を含めたものを遺留分計算の基礎財産に含める必要があります。
第三者に対する贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額が加算されるものとなります(民法1044条1項本文)。なお、当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年前の日より前にしたものについても加算されます(民法1044条1項但し書き)。
他方で、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にしたもののうち、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限って(特別受益に該当する贈与に限って)、加算されます(1044条3項)。
したがって、上記の要件を満たす生前贈与も考慮して遺産の総額を計算するようにしましょう。
また、負担付贈与(1045条1項)や不相当な対価をもってした有償行為(1045条2項)についても加算の対象となることがあります。

③ 債務の控除
被相続人に債務がある場合には、同債務の額を控除します。
なお、相続税や相続財産の管理に関する費用、遺言執行に関する費用はここに含まれません。
保証債務がある場合に、控除されるかが問題となることがありますが、「主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、その履行による出捐を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込みがないような特段の事情が存在する場合でない限り」(東京高判平成8年11月7日判時1637号31頁)ここにいう債務には含まれないものと考えられています。

④ 遺留分の総額を算出する
次に、上記で算定した財産総額(遺留分を算定するための財産の価額)に対して自分の立場に応じた遺留分の割合(2分の1または3分の1)を掛け合わせ、これに法定相続分の割合を乗じます。
これが遺留分として受け取ることができる金額となります。
計算例)
遺産総額が3,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は1/2、子ども2人は各1/4となります。配偶者の遺留分は法定相続分の1/2であるため、次のように算出されます。
- 配偶者の法定相続分:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 配偶者の遺留分:1,500万円 × 1/2 = 750万円

⑤ 遺留分の侵害額を算出する
次に、実際にあなたが遺言や遺産分割協議で受けとることができた遺産額を、先ほど算出した遺留分の金額から差し引きます。その差額が「遺留分侵害額」となります。
遺留分権利者が承継する債務の額(民法第1046条第2項第3号)がある場合には、これを加算します。
例)
配偶者の遺留分が750万円なのに、実際は遺言に基づき300万円しか受け取れなかった場合、その差額450万円が遺留分の侵害額となります。
なお、遺留分権利者が遺贈又は特別受益を受けていた場合には、それらの価額も控除されます(民法第1046条第2項第1号)。
細かい話になりますが、遺留分を算定するための財産の価額の算定において加算される特別受益は、第三者に対するものは1年以内、相続人に対するものは10年以内という期間制限があります(民法第1044条)。
しかしながら、遺留分侵害額の算定において、控除される遺留分権利者が受けた特別受益については、このような期間制限を定める条文はなく、10年以上前に受けた特別受益であっても控除されます。
また、遺産分割の対象財産がある場合には、遺留分権利者の相続分に相当する額(民法第1046条第2項第2号)についても控除します。
遺留分侵害額請求実施時の留意点
① 請求には時効があるため注意
遺留分侵害額請求をする権利には以下のような法律上の期限があります。
この期限を超過すると、請求が認められなくなります。
- 相続開始および遺留分侵害を知った日から1年間
- または、相続開始の時から10年間
② 生前贈与分の調査が必要
遺留分侵害額を算出する際に、生前贈与分を正確に把握することが重要です。銀行口座履歴や不動産登記簿、贈与契約書などを入念に調査しましょう。
③ 相続人間での交渉が困難な場合、調停や訴訟が必要
相続に関するトラブルは感情的な対立が生じやすく、当事者間で話し合いがまとまらないケースもあります。
解決が困難な場合は、家庭裁判所で調停手続きあるいは裁判手続きをすることになります。
遺留分侵害額請求の手続きを弁護士へ依頼するメリット
遺留分侵害額の算出や請求手続きは、複雑な専門知識が必要であり、簡単ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで以下のようなメリットがあります。
- 正確な遺留分侵害額の算出が可能になる
- 時効期限を確認・管理して、遅滞なく手続きが可能に
- 他の相続人との感情的な対立を回避し淡々と交渉を進められる
- 万が一交渉がまとまらない場合でも、調停や訴訟という法的手続きで迅速に解決を図れる
まとめ
遺留分侵害額請求では、正確な財産評価、生前贈与の調査、特別受益の判断、時効期限の管理が重要です。
当事務所では相続に関する豊富な経験と知識を活かし、遺留分侵害額請求手続きを全面的にサポートしております。遺留分でお困りの際は、適切な対応をとるためにもぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。