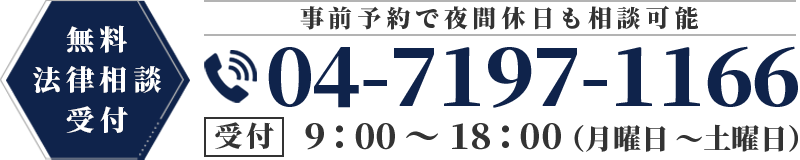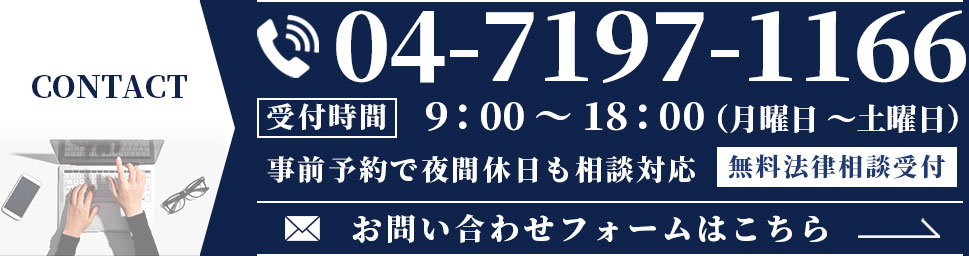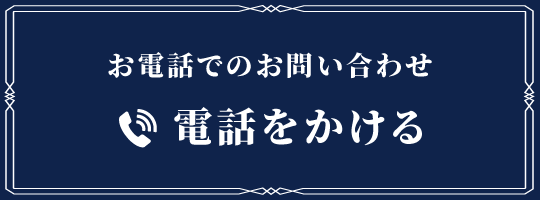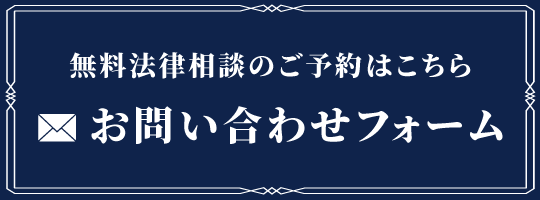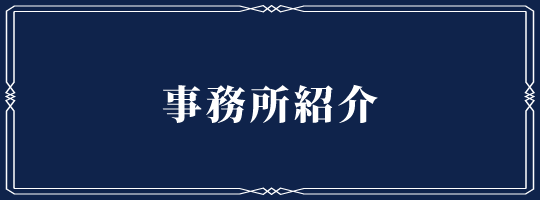相続が発生した際に、遺言書や生前贈与の影響で相続人として本来受け取るべき遺産が十分に確保されなくなった場合、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
この遺留分侵害額請求には一定の期限(時効)が設けられており、正確に把握しておかないと権利を行使できなくなります。
今回は、遺留分侵害額請求の時効について詳しくご説明いたします。
このページの目次
遺留分侵害額請求とは何か
まず、「遺留分」とは法律で定められた相続人(配偶者・子ども・直系尊属など)が最低限受け取ることのできる財産の割合のことを指します。
「遺留分侵害額請求」とは、相続人が遺言などによって自分の遺留分を侵害された場合に、その差額を他の相続人や遺贈を受けた人に対して請求する制度です。
遺留分の割合(例)
| 相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 |
| 配偶者のみ、または子どものみ | 法定相続分の1/2 |
| 配偶者と子ども | 各自の法定相続分の1/2ずつ |
| 直系尊属(父母など)のみ | 法定相続分の1/3 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし |
遺留分侵害額請求の時効とは
遺留分侵害額請求権は民法により時効期間が定められており、この期限を過ぎると請求権自体が消滅してしまいます。具体的な時効期間は以下の2種類があります。
① 相続の開始および遺留分侵害を知った日から「1年以内」
民法上、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」(民法1048条前段)と定められています。
遺留分侵害額請求の時効は、相続開始(被相続人の死亡)および自分の遺留分が侵害されている事実を知ってから「1年以内」と法律で定められています。
この1年の時効はかなり短期間であるため、少しでも自分の遺留分侵害に気付いたら速やかに対応が必要となります。
② 相続の開始から「10年間」
上記の1年以内という条件とは別に、自分の遺留分侵害に気付かなくても、相続が開始した時点(被相続人の死亡時)から「10年が経過」すると法律上請求が認められなくなります。
これは絶対的な期間であり、特段の事情がない限り延長されることはありません。
遺留分侵害額請求の時効期限の注意点
請求後は速やかに交渉を進める
時効が迫っている場合は、内容証明郵便を迅速に送付し、自らの権利の確保を目指しましょう。
訴訟または調停の検討
相手方が協議に応じない場合や、内容証明に対して何ら応答がない場合は、家庭裁判所で遺留分侵害に関する調停や訴訟を早急に申し立てることが重要になります。
遺留分侵害額請求を行う際の具体的手続き
遺留分侵害額請求を考える際は、まず時効期限を確認し、迅速に以下の手順を行なうことが肝心です。
- 相続財産や遺留分侵害額の正確な計算と評価を行なう。
- 弁護士などの専門家の助言を受け、請求方法や手続きを明確化する。
- 期限が迫る前に内容証明郵便で請求を行ない、正式な請求意思を示す。
- 交渉難航や拒絶された場合には、なるべく早急に家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てる。
遺留分侵害額請求で弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求の手続きは複雑であり、そもそも時効という厳格な期限があることを踏まえると、専門家である弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
弁護士への依頼のメリットは以下の通りです。
- 遺産総額や遺留分侵害額の計算を迅速かつ正確に行える。
- 内容証明郵便や交渉、調停・裁判など一連のプロセスを完全にサポートできる。
- 当事者間の感情的な対立や混乱を抑え、冷静かつ迅速な解決に導ける。
当事務所における遺留分侵害額請求サポート
当事務所では、遺留分侵害額請求の豊富な経験に基づき、以下のようなきめ細やかなサポートをご提供しております。
| サービス内容 | 詳細 |
| 時効期限のアドバイス | 時効までの期間を正確に計算し、速やかな対応を促します。 |
| 遺産調査・遺留分計算等 | 正確かつ迅速に遺留分侵害額を算出します。 |
| 交渉および訴訟対応 | 相手方との交渉支援から裁判手続きまで、包括的に対応致します。 |
| 継続的アフターサポート | 手続き完了後も相続に関連する不安や悩みに対応します。 |
まとめ
遺留分侵害額請求には「1年」と「10年」という2種類の時効があります。遺留分の権利を失わないためにも、早期に専門家へ相談して適切な手続きを進めていただくことが大切です。
当事務所は信頼できる法律のプロフェッショナルとして、真摯に依頼者様をサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。