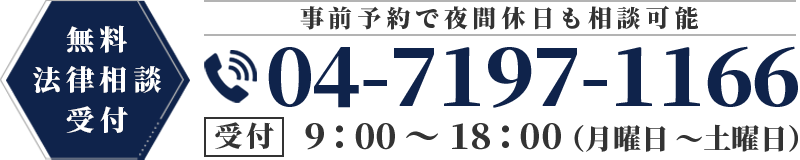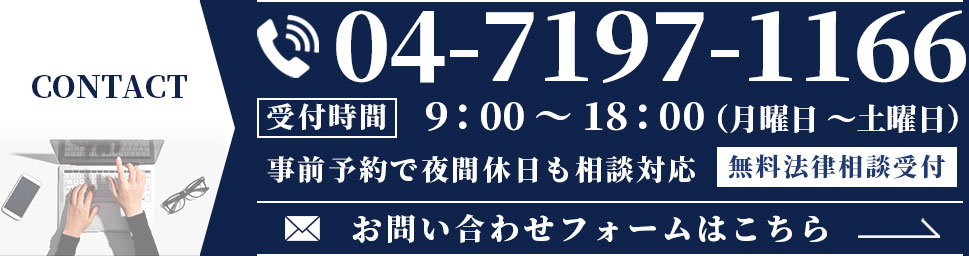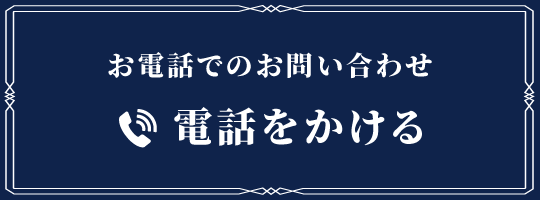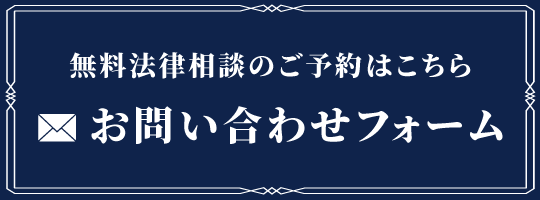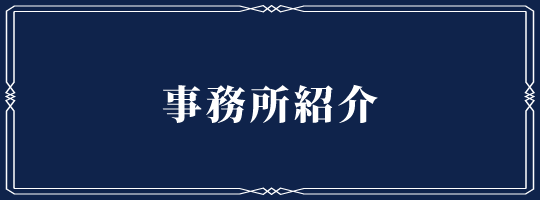ご自身やご家族がお亡くなりになった際、遺言書が見つからない場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。『遺言書がない』という状況では、法律上定められた形で、相続の手続きが進められていきます。
この記事では、遺言書がない場合の相続手続きの流れや注意点について詳しくご説明します。
このページの目次
遺言書がない場合の相続の基本原則
遺言書が存在しない場合、相続人間で遺産の分け方について話し合いを行い、その内容を『遺産分割協議』によって決める必要があります。
相続には民法で定められた『法定相続分』という基準があります。
もっとも、相続人同士が納得して合意すれば、必ずしも法定相続分通りに分ける必要はありません。
① 法定相続人の確定
まず遺産分割協議を行う前に、『法定相続人』を正確に確定させることが重要です。
法定相続人とは、法律で決まった遺産を承継する権利を持つ人のことで、主に下記の方々が対象となります。
- 配偶者(常に法定相続人となります)
- 子(子ども・孫などの直系卑属)
- 直系尊属(父母、祖父母など)
※子や孫など直系卑属がいない場合のみ法定相続人となります。 - 兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合のみ法定相続人になります)
相続関係を特定するためには、戸籍謄本などを取得し、血縁関係を確認したり、相続人が正確に誰であるか確定させる必要があります。
② 法定相続分の確認
次に、相続人それぞれの基本的な相続割合である『法定相続分』を確認します。
例えば、相続人が「配偶者」と「子供(2人)」の場合は、配偶者が1/2、残りの1/2を2人の子が均等(1/4ずつ)に相続することになります。代表的なパターンを下表でご紹介します。
| 相続人 | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 子が残りの1/2を等分 |
| 配偶者と直系尊属(親や祖父母) | 2/3 | 直系尊属が残りの1/3を等分 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹が残りの1/4を等分 |
遺産分割協議の進め方
遺言書がない場合には、『遺産分割協議』によって遺産の具体的な分け方を話し合いで決定します。
手続きの流れやポイントを以下で説明します。
① 相続人の範囲の確定
上記のとおり、相続人の範囲を確定させます。
法定相続人のほか、包括受遺者(民法990条)や相続分の譲受人がいる場合には、遺産分割協議の当事者となります。さらに、下記のとおり代理人等が当事者となる場合があります。
- 当事者の意思能力や行為能力に問題がある場合
→ 成年後見人 - 当事者が不在である場合(従来の住所又は居所を去った場合)
→ 不在者財産管理人 - 当事者が未成年である場合
→ 親権者又は未成年後見人

② 遺産の内容の調査と評価
まず、遺産の範囲を調べましょう。不動産の登記事項証明書、預貯金通帳等、相続対象となる財産内容を把握します。
この際、各財産の金銭的価値を客観的に評価する必要があります。不動産については固定資産評価証明書や不動産の鑑定評価等を用いて金額を算出します。
遺産分割の対象となる財産
遺産分割の対象となる財産は、原則として以下の基準を満たす相続財産です。
- 相続開始時に存在したこと
- 相続開始時に被相続人に帰属していたこと
- 積極財産であること
- 遺産分割時に存在すること
- 未分割であること
具体的には、上記の条件を満たす相続財産である不動産、金銭、動産、有価証券、預貯金債権、債権、ゴルフ会員権、貴金属、暗号資産等が遺産分割の対象となる財産となります。
遺産分割の対象とならない財産
一身専属的な権利(民法第896条ただし書き)と祭祀財産(民法第897条)については、そもそも相続財産に含まれず、遺産分割の対象財産となりません。
また、遺産に収益物件があった場合に当該物件から生じた賃料債権や、被相続人が事故等で死亡した場合の損害賠償請求債権等の金銭債権については、法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するもの(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)とされる為、遺産分割協議の対象財産とはなりません。
生命保険金についても、対象財産には含まれず、死亡退職金については、厳密には死亡退職金の規定によるということにはなりますが、多くの場合、対象財産には含まれません。
相続開始後に処分された財産についても、原則としては遺産分割の対象財産とはなりません。もっとも、例外的に共同相続人全員の同意によって、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(民法906条の2第1項)。
また、共同相続人の一人又は数人によって財産が処分されたときは、当該相続人については、同意がなくとも、他の共同相続人全員の同意があれば遺産とみなすことができます(民法906条の2第2項)。
なお、遺産分割の対象とならない財産についても、一部の財産については、遺産分割協議や調停において、当事者の合意があれば、これを含めて遺産分割を成立させることは可能です。

③ 遺産分割協議書の作成と合意
相続人全員で話し合いをして、具体的な財産配分について合意した内容を『遺産分割協議書』として作成します。この書面には相続人全員が署名および実印で押印し、各自の印鑑証明書を添付する必要があります。
- 財産ごとにどの相続人がどの財産を承継するのか明確に記載しましょう。
- 口頭で合意するだけでは法的効力が乏しいため、書面化することが重要です。

④ 遺産分割協議がまとまらない場合はどうする?
協議がまとまらず話し合いが困難な場合、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用する必要があります。
家庭裁判所での手続きは法的な判断に基づいて適切な財産の分配を行いますので、必要に応じて弁護士への相談がおすすめです。
相続税の申告・納付
相続開始後、原則として10ヶ月以内に相続財産に対する相続税の申告と納付を行う必要があります。
相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)がありますが、この金額を超える財産がある場合、相続税の手続きが必要です。複雑な手続きや計算が伴いますので、専門家(税理士)への相談をお勧めします。
遺産分割協議で見落としがちなポイント
以下の点はトラブルを予防するためにも必ずチェックしてください。
- 債務(借金など)も相続対象になるため、財産とともに明確化する必要があります。
- 財産調査を怠り、一部の財産が未発見の場合、後日再協議が必要になることがあります。
- 相続放棄や限定承認の選択肢もありますが、期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)があるため注意が必要です。
まとめ
遺言書が見つからない場合でも、しっかりと法的手続きを経て円満に相続を完了させることができます。ただし、遺産分割協議が円満に進まないケースでは、第三者である弁護士のサポートが有効です。
当事務所では遺言作成だけでなく、遺産分割協議を含め相続発生後の手続きについても、親身にサポートいたします。相続に関するお悩みや疑問をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。