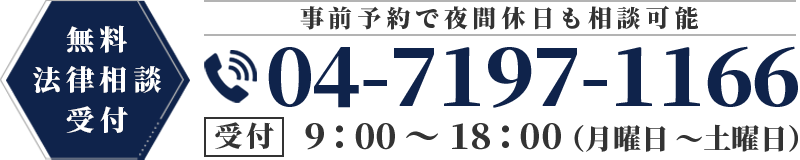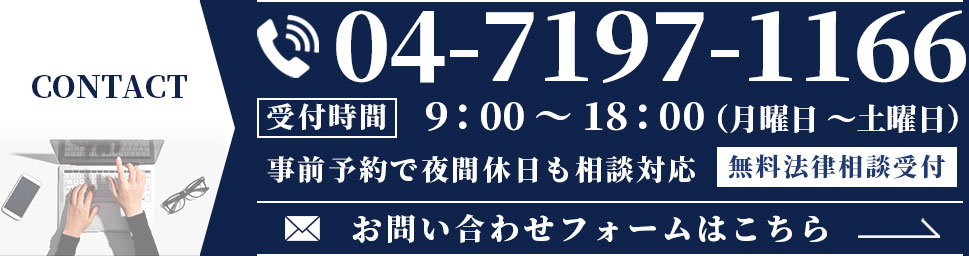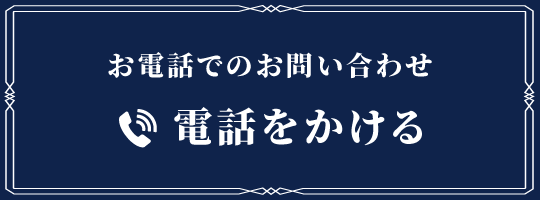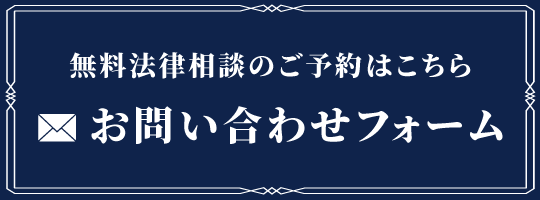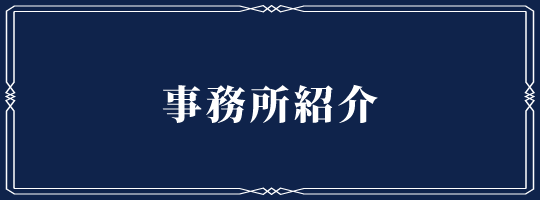自筆証書遺言は、遺言者ご自身が手軽に作成できる遺言の形態として広く知られています。一方で、有効とされるためには法的な要件を満たした正しい手順が必要です。
せっかく作成した遺言書が無効となり、ご自身の意思が実現されない事態を防ぐために、自筆証書遺言に求められる要件を詳しく解説します。
このページの目次
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、ご自身自らの手で、全文を記載して作成する遺言書のことです。公証役場を介さずに作成できるため手軽で費用もかからない点が大きなメリットとして挙げられます。
- 公証役場などに行く必要がない
- 費用がほとんどかからない
- いつでも手軽に書き換えができる
しかし、法律で定められた要件を満たさない場合、遺言書自体が無効になるリスクもあるため、注意が必要です。
自筆証書遺言の有効性に必要な3つの基本要件
民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定しており、
- 全文の自書(例外については後述)
- 日付の自書
- 氏名の自書及び押印
の要件を満たして作成する必要があります。
それぞれをさらに詳しく解説いたします。
① 全文を自筆で記載すること
自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が全文を自分の手で書かなければなりません。パソコンやスマートフォンで作成・印字したものは無効となります。
もっとも、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書によることを要しません(民法968条2項前段)。
したがって、自筆証書遺言にこれと一体のものとして添付する財産目録については、パソコンやワープロ等を用いてタイプされたものでも認められます。
なお、この場合(自書によらない財産目録を添付する場合)には「目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない」(民法968条2項後段)とされています。
そのため、財産目録の各ページに必ず本人の署名および押印が必要です。この新たな点にも十分注意しましょう。
- 自筆部分には鉛筆などの改ざん可能な筆記具を避け、消せないペン(ボールペンや万年筆が望ましい)を使いましょう。
- 訂正する場合も法律で定められた訂正方法に沿う必要があります。加除その他の変更の場所を記載(指示)したうえで(①)、これを変更した旨(削除や追加、改める場合はその文言)を付記し(②)、その(①及び②の)記載がされた箇所に署名をする(③)必要があります。その上で、「変更場所に」押印をする必要があります(④)。
- 通常の文書の訂正の際は、訂正する文言を二重線で消したうえで、横に訂正後の文言を記載し、押印するといった方法が取られることがありますが、このような方法とは異なった方式が求められていることに注意が必要です。

② 正確な日付を記載すること
遺言書の作成日付は、必ず書かなければならない基本的な要件です。日付は西暦であっても、和暦であっても構いませんが、単に「令和7年4月」など、日が特定されない場合は無効となる可能性があります。
必ず「令和7年4月10日」など、明確に日付を特定して記載しましょう。
判例(昭和54年5月31日民集33巻4号445頁)においても、「証書の日附として単に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、そのような自筆証書遺言は、証書上日附の記載を欠くものとして無効である」と判断されています。
日付記載時の注意点:
- 和暦、西暦のどちらでも有効ですが、日付をはっきり記載することが重要です。
- 後日、複数の遺言書が発見された際、最新の日付のものが有効となりますので、最新の作成日時が明確に記された遺言書をお勧めします。

③本人の署名と押印を行うこと
遺言者自身が遺言書に自筆で署名し、必ず押印をしなければなりません。署名は戸籍上の正式な氏名であることが一般的ですが、本人を明確に特定できる筆名・雅号・通称でも認められる場合があります。ただし、争いを避けるためには戸籍上の正式氏名を記載することを推奨します。
押印については実印である必要はありません。また、遺言書が複数枚に及ぶ場合であっても、押印はその内の一枚にされていれば足りるものと考えられています。
- 署名時には一筆書きで漏れなく書き、押印の印影は鮮明にすることが重要です。
- 文章末尾に署名・押印することが一般的です。
遺言書の適切な保管方法
遺言書の保管については特に規定がありませんが、重要な書類であるため適切な保管が大切です。最近では法務局に遺言書を保管する制度(2020年7月から実施)が設けられました。
この制度のメリットは以下の通りです。
- 遺言書の原本を法務局が確実に保管するため、紛失や改ざん・隠匿のリスクがありません。
- 法務局で保管した遺言書は家庭裁判所の「検認」手続きが不要ですので、相続手続きが早く進められます。
法務局に保管する場合には、手数料として1通あたり3,900円が必要です(2025年現在の料金)。
自筆証書遺言の作成でよくある間違い・注意点
以下に、自筆証書遺言に関連してよくみられる間違いについて説明します。
これらについても十分注意しましょう。
- 内容が曖昧
(例:複数の不動産がある場合に、単に不動産を相続させるとするなど。財産を特定し具体的に記載するよう心がける) - 遺言内容の訂正方法が間違っている(訂正箇所や記入方法に不備がある)
- 日付の記載漏れや署名・押印漏れがある
弁護士への相談を推奨する場合
ご自分で遺言書を作成するには手間と時間も必要であり、ご不安もつきものです。
また、相続人間でのトラブルを防ぐためにも、弁護士などの専門家に相談し、サポートを受けながら作成されることをお勧めします。
まとめ
自筆証書遺言が法律上有効となるためには、全文自筆、日付の明記、署名押印の3要件を必ず満たす必要があります。さらに訂正や保管にも十分注意しなければなりません。
ご自身の大切な財産を円滑に次世代へと託すためにも、遺言書の作成について疑問や不安がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。遺言書作成の段階から手厚くサポートいたします。