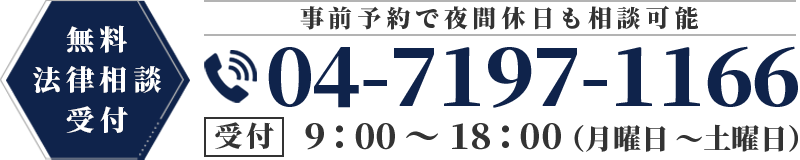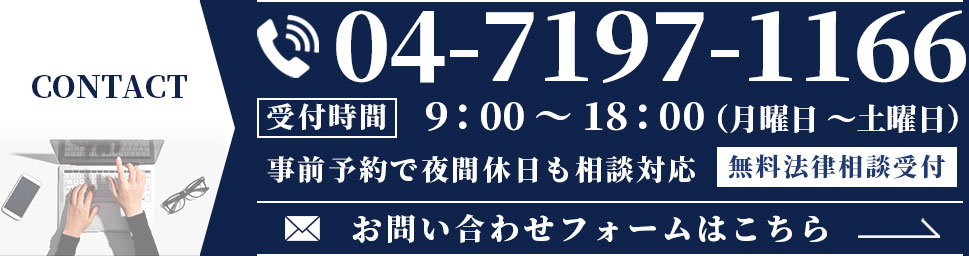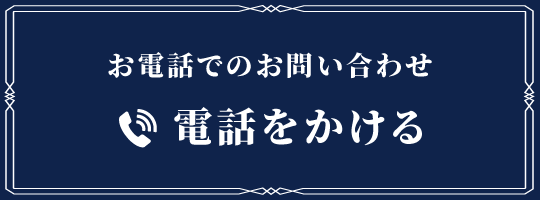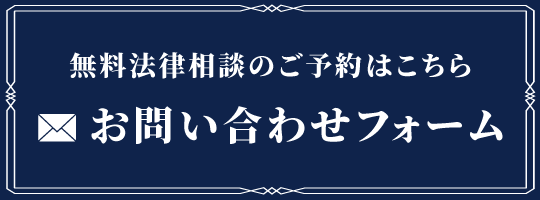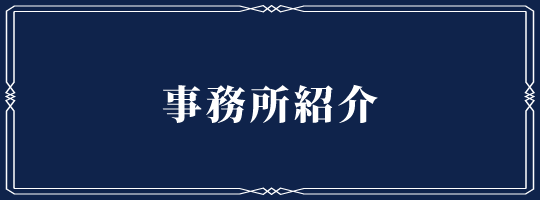ご自身の財産を、ご自身の意思通りに確実に相続人へと引き継ぐためには、正しく有効な遺言書を作成することが非常に大切です。
しかし、遺言書を作成しても法律で定められている形式を満たしていないと、有効にならずに遺志を実現できないことがあります。
そこで、今回は遺言書を法律に基づいて正しく作成する方法を具体的にご説明いたします。
このページの目次
遺言書の種類
遺言の種類(方式)としては、下記の7種類となります。
- 自筆証書遺言(民法968条)
- 公正証書遺言(民法969条)
- 秘密証書遺言(民法970条)
- 危急時遺言(民法976条)
- 伝染病隔離者遺言(民法977条)
- 在船者遺言(民法978条)
- 船舶遭難者遺言(民法979条)
遺言書の主な種類と特徴
以下、一般的な遺言である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の遺言について、それぞれの特徴と作成方法をご紹介します。
| 遺言書の種類 | 特徴・メリット | デメリット |
| 自筆証書遺言 | 費用がかからず手軽に作成可能 | 書き間違いで無効になる可能性がある。家庭裁判所で「検認」手続きが必要。 |
| 公正証書遺言 | 公証人が遺言書作成に協力し、無効となるリスクが低い。検認手続きが不要。 | 公証役場での作成手数料がかかる |
| 秘密証書遺言 | 遺言の存在だけが公証役場で証明され、内容は非公開にできる | 内容の間違い等を公証人が確認しないため、無効になるリスクがある。検認手続きも必要。 |
ここでは、特に作成頻度の高い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について詳しく解説いたします。
自筆証書遺言の正しい作成方法とは?
① 全文の自筆作成(財産目録を除く)
遺言者自身が全文を手書きで作成することが求められます。パソコン等の印字では無効になります。
ただし、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書によることを要しません(民法968条2項前段)。自筆証書遺言にこれと一体のものとして添付する財産目録についてはパソコンやワープロ等を用いてタイプされたものでも認められます。
なお、この場合(自書によらない財産目録を添付する場合)には「目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない」(民法968条2項後段)とされています。

② 作成日時の明記
「令和◯年◯月◯日」と正確に作成された日付を記載します。日付は西暦であっても、和暦であっても構いません。
単純に「令和◯年◯月」と書くだけでは無効になることがあります。
判例(昭和54年5月31日民集33巻4号445頁)においても、「証書の日附として単に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、そのような自筆証書遺言は、証書上日附の記載を欠くものとして無効である」と判断されています。

③ 氏名の署名と押印
- 署名は戸籍上の本名を推奨します。ただ、戸籍上の氏名に限られるものではなく、通称やペンネーム、婚姻前の氏といったものであっても、遺言者を特定できる場合には、有効です。
- 押印は認印でも有効ですが、実印が確実です。
例文)
- 遺言者●●(自身の氏名)は、次のとおり遺言します。
- ○○市□□町△丁目△番△号の自宅建物及びその土地は長男の○○○○(氏名)に相続させる。
- 令和◯年◯月◯日 ○○○○(署名)印

④ 保管方法に注意する
保管については、自宅保管が一般的ですが、法務局での保管制度を利用することも可能(2020年7月導入)で、この場合、裁判所での検認も不要というメリットがあります。
公正証書遺言の正しい作成方法とは?
公正証書遺言は、公証役場で作成する方式の遺言書です。公証人が関与して作成するため、遺言が無効になる可能性が低いというメリットがあります。
作成手順は次の通りです。
① 公証役場に連絡して事前準備をする
- 遺言内容や財産の詳細を整理して、公証人との面談日時を決定します。
- 必要書類(戸籍謄本、不動産登記簿謄本、印鑑証明書など)を準備します。

② 証人2人の準備
- 遺言作成時に、相続人以外の者2名以上を証人として立ち合わせる必要があります。
- 身内(相続人の配偶者や子)などは証人にはなれません。公証役場で紹介してもらえる場合もあります。

③ 公証役場での遺言書作成
- 遺言者が遺言内容を口述し、公証人が書面を作成した後、遺言者及び証人は内容が正しいか確認します。
- 公証人・証人が署名押印し、最後にご本人が署名押印します。
④ 手数料の支払い
手数料は遺産総額に応じて、公証役場で定められています。
目安としては、遺産総額5,000万円で約2~3万円程度となります。
遺言書作成の際に誤りが多い注意点について
- 曖昧な表現を避け、はっきりとした表現で財産の記載をしてください。
- 相続開始後の紛争を避けることを望まれる場合は、遺留分(一定の割合で相続人に認められる最低限の遺産)を考慮することが大切です。
- 遺言執行者(遺言を実現するために指名される人)を指定しておくと、相続手続きが円滑に進みます。
- 定期的(2〜3年に一度)に内容を見直すことが推奨されます。
まとめ
遺言書は形式を少しでも間違えると無効になるリスクがあります。正しい遺言書作成には法律に基づく細かな手続きが必要となるため、不安な方は専門家への相談を行うことをおすすめします。
当事務所は遺産相続と遺言書の作成について豊富な実績があります。遺言書作成にお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。