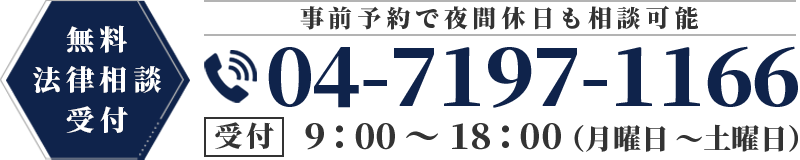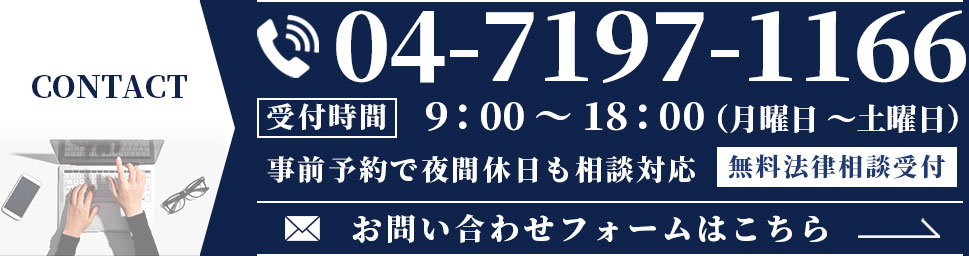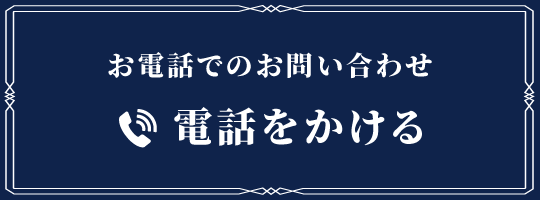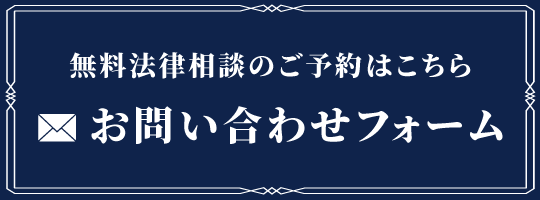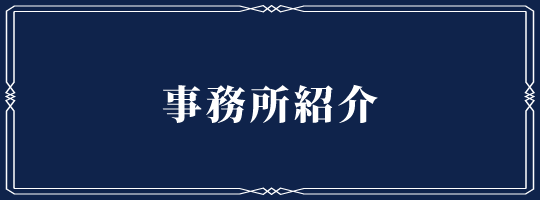相続が発生すると、被相続人の財産が相続人に承継されます。財産には預貯金や不動産などプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。
この際に、負債(相続債務)の処理方法を誤るとトラブルや不利益が発生する可能性があります。
ここでは、遺産分割の際に相続債務をどのように扱い、分割するべきかの方法をわかりやすく解説します。
このページの目次
相続における負債とは?具体的な内容
相続において「負債(マイナスの財産)」として取り扱われる主なものは、以下のような内容があります。
- 住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどの各種借入金
- 個人同士の借金(親族や友人からの借入金)
- クレジットカードの未払い債務(キャッシングやリボ払い含む)
- 未払いの税金(所得税・住民税・固定資産税など)
- 未払いの医療費や介護施設等の利用料
- 損害賠償金
- 保証債務(誰かの連帯保証人となっていた場合)
これらの相続債務がある場合、相続人はその取扱いについて慎重に検討する必要があります。
相続債務の基本的な考え方と注意点
金融機関への問い合わせ
被相続人が取引していた金融機関に、借入金や未払いの利息などを確認します。
税務署への問い合わせ
被相続人の未払いの税金(所得税、住民税など)を確認します。
信用情報機関への問い合わせ
被相続人の信用情報を確認し、借金やクレジットカードの利用状況などを把握します。
被相続人の関係者への聞き取り
被相続人の友人や知人、勤務先などに、借金や保証債務に関する情報を聞き取ります。
相続債務の基本的な考え方と注意点
相続債務の種類
相続される債務は、大きく「可分債務」と「不可分債務」の二つに分けることができます。
可分債務
- 金銭債務(借金、未払いの医療費など)のように、分割可能な債務です。
- 各相続人が法定相続分に応じて当然に承継し、各相続人は、法定相続分に応じた支払い額を負担することになります。
不可分債務
- 不動産の登記移転義務や、物の引渡債務のように、分割できない債務です。
- 各相続人が連帯して債務全体を弁済する責任を負います。
なお、法定相続分とは、法律で定められた各相続人が相続できる割合のことで、具体的には以下のとおりです(配偶者がいる前提の場合)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
| 配偶者+子ども | 1/2 | 子ども全員で1/2 |
| 配偶者+父母など直系尊属(子どもがいない場合) | 2/3 | 父母等が1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹(子ども・直系尊属がいない場合) | 3/4 | 兄弟姉妹が1/4 |
負債は債権者から相続人全員に請求可能
注意すべき点は、債権者(金融機関やカード会社など)側は、相続人の一人に対して、負債の全額返済を請求することができます。これを「連帯責任(連帯債務)」と言います。
つまり、遺産分割で「負債は兄弟のうち長男が全て引き受ける」と取り決めをしたとしても、そのことを債権者に主張しても効力はありません。債権者との合意(免責的債務引受等)を行わない限り、負債の連帯責任は解消されません。
負債を弁済するための具体的な方法
① 債務引受を活用する方法
特定の相続人に負債の全額を承継させたい場合には、その相続人が債務を引き受ける「債務引受」を行います。これには、「免責的債務引受」と「併存的債務引受」の2種類があります。
- 免責的債務引受:
債権者との間で取り決めを行い、他の相続人の負担を完全に免除してもらう方法(債権者の承諾が必要) - 併存的債務引受:
特定の相続人が主たる返済義務を負うが、債権者からすべての相続人に請求される可能性は残る方法
② 遺産の中から負債を弁済する方法
預金や不動産などのプラスの遺産が十分にある場合は、遺産分割協議において、先に負債を完済することで、マイナスの財産をゼロの状態にすることが望ましい解決法です。
負債を返済後に遺産を分割すれば、トラブルの可能性が低くなります。
③ 相続放棄を検討する方法
被相続人の負債が遺産(資産)を超える、いわゆる「債務超過」の状態の場合には、「相続放棄」を考えることも選択肢の一つです。
相続放棄をすると、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて引き継がないことになります。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申立てなければなりません。
相続債務についてよくあるトラブル事例と注意点
- 「遺言書で負債を分割指示しても債権者への効力はないので返済義務は残る」ことを知らずにトラブルになる
- 特定の相続人が負債の返済を怠ったため、債権者が他の相続人に請求を行い、兄弟姉妹間のトラブルとなる
- 相続放棄する期限を過ぎてしまい、債務超過状態でも返済義務を負ってしまう
こうしたトラブルを未然に防ぐために、相続人同士でしっかりと話し合いをして遺産分割協議書を作成するとともに、必要に応じて債権者と協議・交渉を行うことが大切です。
まとめ
相続債務が存在する場合には、各相続人の負担を明確にし、慎重に進めることが非常に重要です。複雑な法律問題も多く含まれるため、弁護士など専門家に早めにご相談することを強くおすすめします。
当事務所でも、負債を含む相続問題を豊富な経験に基づいて対応しております。相続債務の処理の方法についてご不安のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。