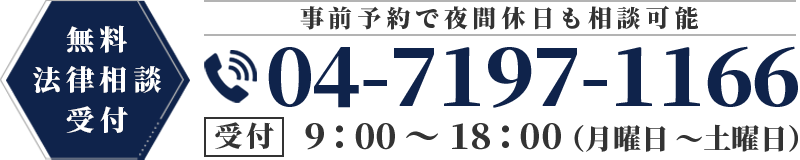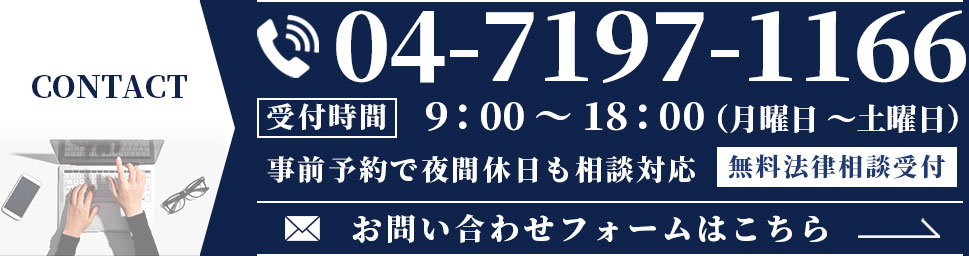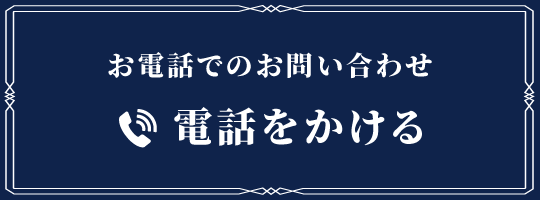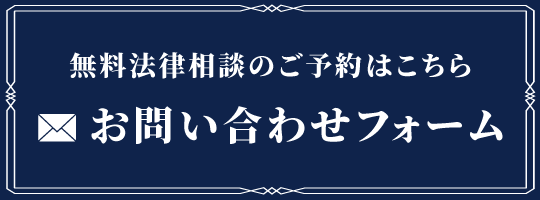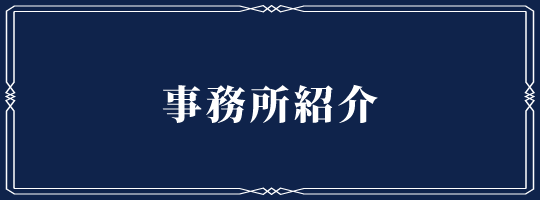相続では、被相続人の財産の維持又は増加について特別な貢献や援助を行った方は、通常より多くの相続分を認められる場合があります。これを「寄与分」といいます。
しかし、寄与分を主張するためには一定の条件が必要であり、その過程でトラブルが起きるケースも少なくありません。
本ページでは、遺産分割の際に寄与分を主張するための要件、具体的な注意点について分かりやすくご案内します。
このページの目次
寄与分とは何か?
民法904条の2第1項は、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」と規定しています。
「寄与分」とは、相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、その相続人に対して法的に認められた特別な相続分です。具体的には、以下のような貢献が該当する場合があります。
- 被相続人の介護や看護を長期間無償で行った場合
- 家業の手伝いや経営に携わり、財産を維持または増加させた場合
- 借金の弁済に協力し財産の減少を防いだ場合
特別な貢献が明確に認められれば、その相続人には通常の法定相続分よりも多くの相続財産が認められます。ただし、寄与分が認められるには一定の厳しい基準や要件を満たす必要があります。
寄与分が認められるための条件・要件
寄与分が認められるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 特別な貢献の内容が、「通常の親族間で期待される範囲を超える」ものであること
- 貢献が具体的に財産の維持又は増加に結びついていること(明らかな経済的利益や節約効果があること)
- 貢献が無償で行われていること(相応の対価や報酬を受け取っていない)
- 貢献が共同相続人或いは共同相続人の履行補助者と評価できる者によるものであること
これらの条件を一つでも欠く場合、法律的に寄与分が認められない可能性もあります。
寄与分を主張するときの注意点
注意点① 客観的で十分な証拠資料を準備する必要がある
寄与分は基本的に相続人それぞれの合意が必要で、合意が難しい場合には家庭裁判所での調停・審判を経ることになります。寄与分が認められるためには、「特別な貢献」を具体的に証明する客観資料を揃えることが絶対条件となります。
具体的には以下の資料を用意しましょう。
- 介護や看護をしていたことを示す介護記録や医療関係の記録
- 財産管理を行っていた銀行通帳、家計簿、領収証などの書類
- 家業や事業への貢献が分かる帳簿や収支計画書、勤務記録
- 第三者(親戚や近隣住人等)からの証言や書面
注意点② 「一般的な親族として当然の範囲」との違いを明らかにする
親族として被相続人の介護などを行うこと自体は性質上一般的なことであり、当然の親族間の助け合いとみなされる場合もあります。
そのため、寄与分が認められるためには、一般的に期待される範囲を明確に超えていることを具体的に示さなければなりません。
- 例えば、長期間(一般的には数年以上と言われます)自宅で被相続人の介護を行った
- 毎日のように病院への送迎や日常生活の援助を無償で継続的に行った
- 会社や家業を自ら率先して手伝い、多額の利益を生む経営改善をした
注意点③ 寄与分の請求には時効があるため注意が必要
寄与分は、相続開始から一定期間内に主張することが必要です。原則として相続開始後の遺産分割協議の中で主張しますが、遺産分割が終了した後に新たに寄与分を主張することは難しくなります。
寄与分の主張を検討している方は早めに弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。
注意点④ 他の相続人との感情的なトラブルに発展しないよう配慮する
寄与分を主張することで、他の相続人との関係悪化や感情的対立が生じる可能性があります。
遺産分割協議の際には、弁護士など第三者が協議に入り、中立的かつ客観的な話し合いを進めることでトラブルを未然に防止するよう工夫が必要です。
寄与分を主張する際のフローとポイント
| ステップ | 内容とポイント |
| 寄与内容の整理 | 寄与の内容を具体的に整理し、貢献が財産の維持・増加にどの程度寄与したかを記録。 |
| 資料・証拠の準備 | 寄与を裏付ける客観的な証拠書類や第三者からの証言を確保する。 |
| 相続人間の話し合い | 出来るだけ早い段階で、他の相続人に寄与分について説明・合意を得る働きかけを開始。 |
| 調停・審判の申し立て(必要に応じて) | 話し合いがまとまらない場合は裁判所に寄与分について遺産分割調停或いは寄与分を定める処分調停を申し立てる。 |
まとめ
遺産分割において、寄与分を主張するには客観的な証拠資料の準備や法的要件の明確な理解が重要となります。主張する内容によっては手続きが複雑になりますので、早めに相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。
当事務所では相続問題に広く対応しており、寄与分についての交渉・アドバイスにも実績があります。寄与分についてご不明点やお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。適切な方法で円満な遺産分割のサポートをいたします。