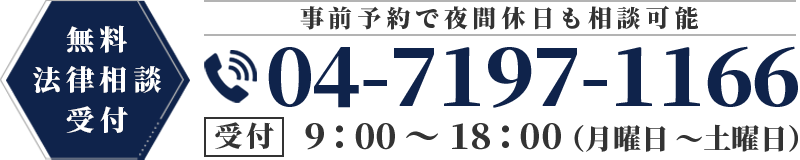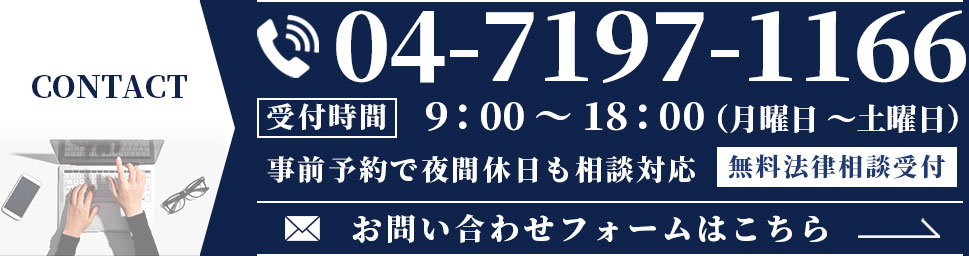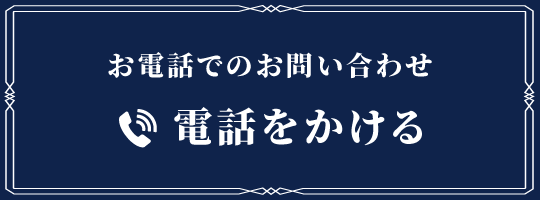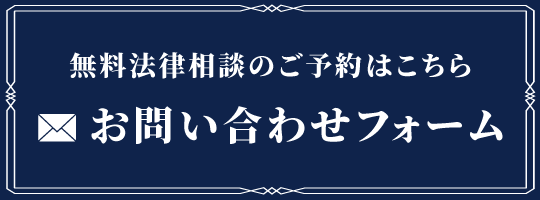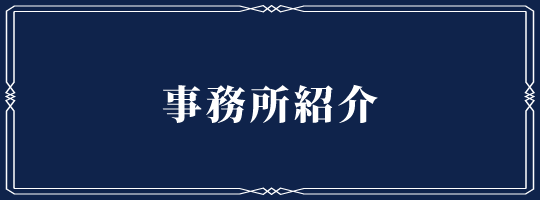遺産分割協議は、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人間でどのように分けるかを話し合うものです。
ただ、財産を巡ることになると、相続人間の利害関係の違いや感情的な対立が生じやすく、話し合いが成立しないケースも珍しくありません。
このページでは、もし遺産分割協議がうまくいかなかった場合の対応方法について、段階を追って分かりやすく解説いたします。
このページの目次
遺産分割協議が不成立になる主な原因とは?
遺産分割協議がまとまらない原因として、以下のような例が挙げられます。
- 相続人の間で希望や主張が対立してしまい、話し合いによる折り合いが見つからない
- 財産内容やその評価額に関して相続人の間で意見が異なりまとまらない
- 一部の相続人が協議に参加せず、話し合いが進まない
- 寄与分や特別受益の有無及び評価で揉めてしまう
こうした状況で相続問題が長期化すると、関係がさらにこじれる原因にもなりかねません。そこで、迅速かつ適切に問題を解決するために、以下の対応策を検討することをおすすめします。
対応策① 家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議が行き詰まりを見せた場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。
この調停では、中立的な立場である調停委員が相続人間に入り、話し合いによる円満な解決を目指します。
| 場所 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立人 | 相続人の一人又は複数 |
| 相手方 | 申立人の他の相続人全員 |
| 申立て費用 | 遺産の総額によりますが、1,200円~ |
| 調停期間 | 半年から2年程(争点の多さや当事者の人数により異なります) |
遺産分割調停の特徴として、調停委員が中立的立場で双方の事情を聞きながら、解決策を模索してくれます。
また非公開で行われるため、プライバシーを守ることもできます。
対応策② 調停が不成立の場合は審判による解決を目指す
遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合は、「遺産分割審判」に移行します。これは調停と異なり、話し合いではなく裁判所(裁判官)が最終的な判断を下す手続きです。
- 遺産分割審判では、裁判官が証拠書類や相続人の主張を元に財産分割の内容を決定します。
- 期間は個々のケースにより異なりますが、約半年~1年半程度はかかることを想定しておいた方がいいでしょう。
- 審判の内容は、判決と同じ法的拘束力をもちます。相続人には従う義務が生じます。
ただし、審判手続きでは裁判所が下した判断に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に即時抗告が可能です。そのため審判がすぐに確定しないこともあります。
対応策③ 遺産分割協議が不成立にならないよう事前に予防する対策
実際に調停や審判に進まなくて済むよう、以下のような予防策をとっておくことも重要です。
- 財産の内容や価値を明確にしておく(財産目録・預貯金や株式・不動産の評価額など)
- 遺言書やエンディングノートを用意し、スムーズな分割が行えるようにしておく
- 生前贈与や特別受益の有無を明確に記録しておく
- 家族間で生前に積極的に話し合いを行い、遺産分割に対するお互いの意思を確認する
ケーススタディ:対応策を分かりやすくした実例
| 対応策 | 概要・内容 | かかる期間 | 費用の目安 |
| 遺産分割調停 | 家庭裁判所の調停委員による中立的な仲介 | 約半年~2年程度 | 裁判所への申立費用:約1,200円~ 弁護士費用:着手金約20~30万円程度、成功報酬(5~20%程度) |
| 遺産分割審判 | 裁判官の判断による強制的な解決方法 | 半年~1年半程度 | 主に弁護士費用(着手金、成功報酬)・裁判所費用(書類作成の実費) |
まとめ
遺産分割協議が不成立となった場合でも、家庭裁判所の調停や審判といった解決手段があります。遺産分割手続きが長期間停滞すると、その間の固定資産税の負担や財産管理の手間もかかり、関係性も悪化しやすいため、早期解決を図ることが大切です。
遺産分割協議がまとまらない時は、ぜひ相続問題に詳しい法律の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所では相続・遺産分割問題に多くの経験と実績をもち、依頼者様のお話を丁寧にお聞きし最善の解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。