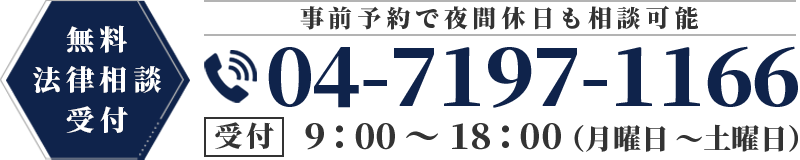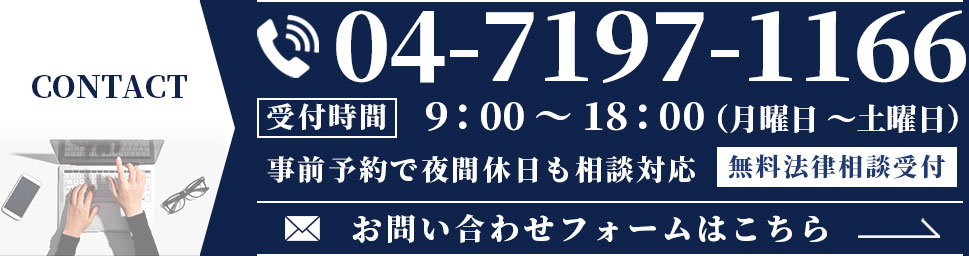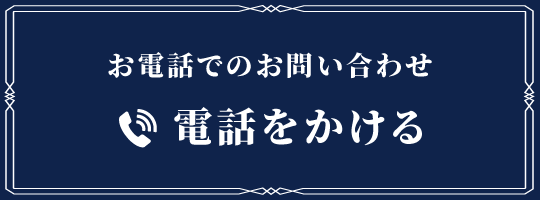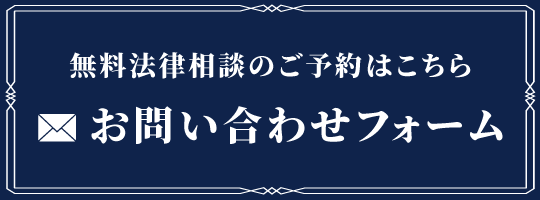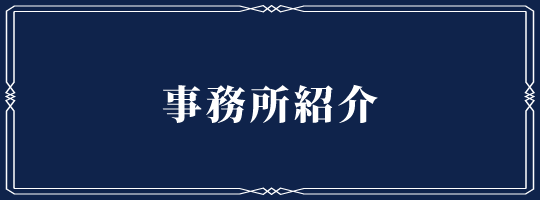ご家族が亡くなられた後、不動産を相続する際に必ず必要となるのが「相続登記(相続による不動産の名義変更)」です。
しかし、いざ手続きを行おうとしても、どのように進めたら良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。
このページでは、不動産の相続登記手続きの流れや必要書類などを分かりやすく丁寧に解説いたします。
このページの目次
相続登記とは何か?なぜ必要なのか?
相続登記とは、不動産所有者が亡くなった後、法務局の登記簿上の所有者名義を相続人に変更する手続きのことです。自動的に登記が変更されるわけではありませんので、相続人が自身で申請を行う必要があります。
2024年4月1日からは「相続登記の義務化」が始まり、相続が発生したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならなくなりました(正当な理由がない限り、怠ると過料の対象になります)。
相続登記の重要性
- 放置した場合、世代を経て相続人が増加し権利関係が複雑化してしまいます。
- 相続登記が行われていないと、将来のトラブルや手続きが難航するリスクがあります。
- 相続税申告を適切に行うためにも欠かせません。
- 2024年4月1日からは「相続登記の義務化」
不動産の相続登記手続きの具体的な流れ
相続登記は、主に以下の手順で進めていきます。
① 相続人の特定と相続財産の把握(事前準備)
まずは誰が相続人であるのかを明確にするために、戸籍謄本を収集・確認する必要があります。
また、不動産の所在地や登記内容を確認するために、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の取得も必要です。
- 戸籍謄本(被相続人の出生〜死亡まで及び相続人全員分)
- 除籍謄本や改製原戸籍謄本(過去にさかのぼり連続して収集)
- 相続財産(不動産)の登記事項証明書(最寄りの法務局またはオンラインにて取得可能)

② 遺言書の確認
遺言がある場合は、基本的にはその内容にしたがって相続手続きを進めます。
そのため、遺言書の有無を確認することが必要です。自筆遺言書の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

③ 相続方法を決定し、遺産分割協議を行う
遺言書が存在せず、相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を取得するかを決定するための協議を行います。
この話し合いは遺産分割協議と呼ばれ、合意の内容を遺産分割協議書に取りまとめます。相続人全員の実印押印及び印鑑証明書添付が必要です。

④ 相続登記に必要な書類を準備する
相続人の特定や遺産分割協議の合意が済んだら、次は具体的な手続きで使う書類を準備します。
相続登記に必要な主な書類一覧
| 書類名 | 取得場所 | 備考・ポイント |
| 被相続人の戸籍・除籍謄本 | 役所(本籍地) | 出生〜死亡まで連続して取得する必要あり |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人住所地・本籍地役所 | 最新のものを準備 |
| 遺産分割協議書(遺言書がない場合) | 相続人間で作成 | 協議書には相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要(印鑑証明書は発行3ヶ月以内) |
| 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 | 被相続人の住所地役所 | 本籍地記載のあるものを請求(発行3ヶ月以内) |
| 相続人の住民票 | 相続人住所地の役所 | 最新のものが必要(発行3ヶ月以内) |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 相続登記申請時の登録免許税の算出に必要(最新年度分) |

⑤ 法務局へ相続登記申請を行う
管轄の法務局に対し、書類を提出し相続登記の申請を行います。
- 管轄法務局(不動産所在地により決定)に直接提出するか、郵送またはオンライン申請を活用できます。
- 登録免許税として固定資産評価額の0.4%を納付します。
- 法務局での手続き期間は、おおよそ1週間〜3週間程度です。

⑥ 登記完了後の確認
登記完了後は、法務局で登記識別情報通知(昔の権利証に相当)が交付されます。
不動産登記事項証明書を改めて取得し、名義が変更されていることを必ず確認してください。
まとめ
相続登記の放置は後々の相続手続きを複雑化させます。
不動産を相続された場合は、このページで解説した流れを参考に、早めの手続きをおすすめいたします。